| �n�_�� |
���̂P��E�o��� |
�ʁ@�u |
���@�l |
�ʐ^�ƎB�e�N |
| ���Ɍ� |
�Ђ傤������ |
��������(�u�����}:10)�Ȃ� 5��5�� (����2��, ���3��) |
���Ɍ� |
�����ېV�Ő��܂ꂽ���Ɍ��̖��́C�u�����l�v�̕���ł���D��̎����̐����œo�ꂷ��D���Ɍ��̂����C���{�s�Ȃǐ_�ˎs���x�C�_�ˎs�Ɩ��Ύs�̈ꕔ�͌㔼�ɉD�܂��͏�肩��쉺���C�_�ˎs�������߂Č��������ĉ��C�Ō�ɒW�H���ɓn�郋�[�g�ŗ���n�����Љ��D
���Ζ����̑���ɂ����܂������j�[�N�ȉw�فC�Ђ��ς肾���т̗��j�͈ӊO�ƐV�����D���ΊC���勴�̊J�ʂ��L�O����1998�N�ɐ��܂ꂽ�D���ۂɖ�������̋��`������ƁC�R�Ɛς܂ꂽ�����ڂɂ��邱�Ƃ��ł���D���Ȃ݂ɉw�ق̋�ނ́C���ςɂ����^�R�Q��Ɩ����сD�F���̃j���W���C�̉ԁC�A�i�S�C�V�C�^�P�C�^�P�m�R�C�ю��ʎq�Ƀ{�[���̗g���������������D
"�{�Ƃ͕��Ɍ��ŏ����������Ă���܂���"�i��������j |
�����Ήw�قЂ��ς肾���� |
 |
2022 |
| �d�� |
�͂�� |
���ɑD(�O����2:09) �Ȃ� 34��20�� (����4��, ����17��, ���13��) |
���Ɍ� |
�������D�k�ƚ���(4)�́u�d�B����v�́C���|�d�B�|���ɍ`�|�������Ƃ������ȃ��[�g���Ƃ�D�����Ƃ��C����o�[�W�����̕��ł��C���łɎw�E����Ă���悤�ɁC�D�����̊�Z���C�ǂ��l���֓n�����̂����^�₾���D�u�d�B�߂���v�ɏo�Ă��鑽���̖����́C�S�����́i��a�c�����쎌�j�ɂ��̂��Ă���D���q�̕l�C���̐l�ې_�ЁC���̖����̍����C����̏��C���e����̕P�H��C�����Ďl�\���m�̐ԕ���߂���Δ��O���ɓ���D�Ȃ��C�ߔg�w�͌��݂̑����w�̂��ƁD
"�d�B�͏��̖����A�������"�i���ɑD�j |
�S�����́@�R�z��B�� |
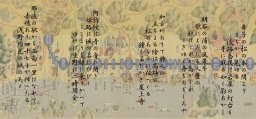 |
2022 |
| �A�n |
������ |
�A�n�̓a�l(�u���a��O2:07) �Ȃ� 3��3�� (����3��) |
���Ɍ� |
�u�A�n�̓a�l�v�́C�u�\�����v�̂��ƁD�ŋ������̗���ƂQ�l���C�a�l���\�������݂����Ƃ̌�G�������āC���b���̒��Ԃł��܂������D�A�n����Ƃ����̂́C�\��U�Ɗ쌀���Ɓw���n�\���ԁx�ɂ���D�d�A�Ƃ����Ă��C�A�n�͉e�������D��背���^�J�[�l�b�g�̕��Ɍ��̗\�j���[�ŁC�A�n�̓X�܂��������蔲���Ă������Ƃ��������D�u�A�n�̓a�l�v�̗̍��́C�L�����o���낤�D�o�̒��̃V���{���ł���C�ۘO�i1881�N�ғ��j�́C�n���̔M�S�Ȓ����ɂ����{�łQ�ԖڂɌÂ����v�䂾�Ƃ������Ƃ����炩�ɂȂ����D�D�y�̎��v������킸���P���������x��Ă��炸�C�^�b�`�̍��œ��{��̍�����~�肽�D�t�F�A�v���[�ɔ���D
"�����ɒA�n�̓a�l�Ƃ��������A�v���Ԃ�̂����l"�i�A�n�̓a�l�j |
�o�ΒC�ۘO |
 |
2015 |
| ��V�� |
���̂��� |
���͍ŋ��̃o�X�K�[���i�j�O�}�n�엎���S�W, ���f�B�A�N���t�g������ (2004)�j |
�L���s |
�����S��蒬�D��艷��D�u��̍�ɂāv�䂩��̎O�؊قɂ́C�u�꒼�Ƃ̊Ԃ��ۑ������D
"��V��Ƃ����ƊO�����L���ł������܂�"�i���͍ŋ��̃o�X�K�[���j |
��艷�� |
 |
2006 |
| ��V��:���ۋ� |
�������� |
���͍ŋ��̃o�X�K�[���i�j�O�}�n�엎���S�W, ���f�B�A�N���t�g������ (2004)�j |
�L���s��蒬���� |
��艷��𗬂���殐�̂S�����ɑ��ۋ����������Ă���D���ۋ��Ƃ����Ă��قƂ�ǔ����Ă��Ȃ��D
"�����ɑ��ۋ��c�c����钬����"�i���͍ŋ��̃o�X�K�[���j |
������ |
 |
2006 |
| �L�� |
�Ƃ您�� |
���b��(��������1:12) 1��1�� (����1��) |
�L���s |
�L���́C�R�E�m�g���ƃJ�o���i���Ă͖��s���j�̒��D��Γ����V���̍ȁC��肭�̏o�g�n�D�肭�┯�˂͓����n��̐������ɂ���D
"��Γ������A�Ȏq�͑����A�n�̖L���ɑ���Ԃ�"�i���b���j |
��肭�┯�� |
 |
2003 |
| �o�y |
���� |
�m�������Ԃ�(�p�쒆�����1:10) 1��1�� (���1��) |
�L���s |
�o�i�������j�D���o�ΌS�o�Β��D�A�n�̏鉺���D���M���̏o�����C�I�����_���v�̒C�ۘO�C�ƘV���~�����ǂ���D�A�n�̓a�l�i�\�����j�́C�A�n�̏��˂�����D�Ƃ���Əo�Δ˂��L���˂����Ȃ��D
"�o�y�s�̂�����ő�J�~���Ă��ĂȂ��i�����j�����̎M���ł��H����"�i�m�������Ԃ�j |
�o�ΎM���� |
 |
2015 |
| �X��S |
�Ђ��݂��� |
���ɑD(�O����2:09) �Ȃ� 2��1�� (���2��) |
�X��S |
���ɒ��������D
"���͒O�g�̕X��S�A�e�͑�X�E�����A�e�̈��ʂ��q�ɕ�"�i���ɑD�j |
�@ |
�@ |
�@ |
| �R |
������� |
�����K��(�u���a��O2:01) �Ȃ� 15��8�� (����2��, ����6��, ���7��) |
�O�g�R�s |
"�O�g�R�R�Ƃ̉���"�ƃf�J���V���߂ʼn̂��C�c�ɂ̋��ʃC���[�W���ł܂��Ă��邪�C������Ƃ����鉺���D��x�����K�₵�Ă��Ȃ��̂����C����Ȑ������炯�̏隬�͌������Ƃ��Ȃ��D
"���̐e��͎Ⴂ���ɒO�g�̎R����o�ė��āA�܂����ɂȂ��ē����ĉ����d���̓X���o������"�i�����K���j |
�R�� |
 |
2004 |
| ���c��R |
�������� |
��ˁE����̊≮(���엎��u��ˁE����̊≮�v, ���|�� (2014)) |
��ӌS�����쒬��R |
�u��ˁE����̊≮�v�́C�_�˖k���ɂ��鐼�J�̔p�z�R�ɒT���ɍs���C�]�ˎ���Ƀ^�C���X���b�v����V��D���c��R��g���̑��C���J�C���J�C���c���Ȃǂ̒n�����o�Ă���D���c�⓺�R�́C2015�N�Ɏj�ՂɎw�肳�ꂽ�D�z�R�̔����́C��������C���c�����ɂ����̂ڂ�D�L�b�G�g�̎���ɑ�ʂ̋���Y�o���C�]�ˎ���͓V�́D����1973�N�܂ő��Ƃ���Ă���C�z�R��Ղ�������D�ԕ��ƌĂ��B������������c���Ă���C�؊ԕ��͓����ł���D���c��R�ւ͓��������w���璖���쒬�R�~���j�e�B�o�X���ʂ��Ă��邪�C���ɂR�ւ����^�s����Ă��Ȃ��D�����̔g���Ȃǂƍ��킹�ĖK�₷��ɂ́C�����ĎR�z�����邵���Ȃ��D
"���J�̒��J�Ƃ����Ƃ��날����́A�̂��瑽�c��R�̍z���̈ꕔ�ŁA�]�ˎ���͂����Ԃ�h�����炵����"�i��ˁE����̊≮�j |
���c��R�Z�\�ԕ� |
 |
2016 |
| �g�� |
�͂� |
��ˁE����̊≮(���엎��u��ˁE����̊≮�v, ���|�� (2014)) |
��ˎs�g�� |
�]�ˎ���Ƀ^�C���X���b�v�����u��ˁE����̊≮�v�̎�l�������́C�Ȃ����̂��k������Ēn�������ɗ������D��яo�����Ƃ���͌���̐犠�����r�D�g�������{�a�̒��ɂ��܂��Ă����D�犠�_���ɂ���Ĕg�������̋����͋����Ȃ�C���i32�N(1425)�Ɍ��Ă�ꂽ�Α����������ۂɈڐ݂��ꂽ�D�g���ւ͎O�c�w�����}�c���o�X���ʂ��Ă��邪�C���ɂR�ւ����Ȃ��̂Œ��ӁD
"�����͂ǂ��ł����|�H�@���J�̔g����"�i��ˁE����̊≮�j |
�g���������� |
 |
2016 |
| ������ |
���������� |
�d�B����(�O����2:06) 1��1�� (���1��) |
�����s����1194 |
�����O�\�O������25�ԎD���D�V��@��ԎR�������D���ÓV�c�̒���ɂ��C���{���������Ă�ꂽ�D�\��ʊω����J��D�܂��C�����V�c�̒���ɂ���u���ɂ́C���ω����J��D��r�͈̂��p�̂Ƃ���D�R��ɂ���C�ԂłȂ��ƍs���̂��h���D
"��\�ܔԂ̎D�����������u���͂�݂�@���܂˂����ǂ̂��Ȃ��ȂɁ@�Ȃɂ����Ȃ݂́@�����ɂ���݂��v"�i�d�B����j |
��������u�� |
 |
1999 |
| �@�؎� |
�ق����� |
�d�B����(�O����2:06) 1��1�� (���1��) |
�����s��{��821-17 |
�����O�\�O������26�ԎD���D�V��@�@�؎R��掛�D���ω���F��{���Ƃ���D�������̎O�d���͍���D
"�@�؎��̂��r�̂��u����܂ӂ��@�ӂ��Ƃ̂���͂��݂ɁT�ĂȂ݂��Ƃ����@���̂̂܂����v"�i�d�B����j |
��掛�O�d�� |
 |
1999 |
| ���ʎR |
���債�Ⴓ�� |
᎕ٌc(�O����2:28)�Ȃ� 11��5�� (����4��, ���7��) |
�P�H�s����2968 |
�V��@�ʊi�{�R���ʎR�~�����D�����O�\�O������27�ԎD���́C����a�̔@�ӗ֊ω���{���Ƃ���D�R��ɂ���C���[�v�E�F�C�ŎQ�q����D���v�P���ԁD
"�c�����S��ۂƖ��Â��A�d�B���ʎR�ɂĐ����Ȃ�"�i᎕ٌc�j |
�~��������a |
 |
1999 |
| �a���� |
���傤���� |
᎕ٌc(�O����2:28) �Ȃ� 4��1�� (���4��) |
�P�H�s���ʂ� |
�ȉ��Q���C���ʎR�̂��Ƃ������܂��D��b�R�ɑ����C���ʎR�ł����\�����ٌc�͕��������D�ʐ^�̋��̈�́C��������ŕ��y�ɖn��h��ꂽ���`������ˁD�a�����͓c�ӂ̂��Ƃ�������Ȃ��D�s���D
"�a�����ʓ��̉��~�ɌÐՂ��₵"�i᎕ٌc�j |
�ٌc���̈� |
 |
1999 |
| �ʓ��̉��~ |
�ׂ��Ƃ��̂₵�� |
᎕ٌc(�O����2:28) �Ȃ� 4��1�� (���4��) |
�P�H�s���ʂ� |
�a�̎R�̓c�ӑ�ꏬ�w�Z�t�߂́C�ٌc�̕��ʓ��X���̉��~�ՂɂȂ�D�a�����Ȃ�ʎY���̈�́C�c�ӎs�����O�ɕ�������Ă���D
"�a�����ʓ��̉��~�ɌÐՂ��₵"�i᎕ٌc�j |
�@ |
�@ |
�@ |
| ���� |
���� |
�\�����킢�i�j�}�����R���N�V����3, �}�����[ (2006)�j |
���̎s |
�鉺������D���݂͂Ђ炪�ȕ\�L�́C���̎s�Ə̂���D�Î����������W���ݖ��ƗK�ې�ɂ��ȂޗL���u�����h�̑f�˂������D�Ŋ��w�͕P�V���{����w�ɂȂ�D
"����̏㓙�̂��ݖ����T�[�b�Ƃ����Ă�����"�i�\�����킢�j |
�ݖ��H��̉��� |
 |
2007 |
| ����:�e��l�̂��{ |
�킫�������܂݂̂� |
������i�s�X��(1890)�j |
���̎s���쒬������ |
����ꂽ����l��u������v�̏I�Ղ́C���삪����ƂȂ�D�e��l�̂��{�Ƃ���̂́C������肳��ɍ���ɂ��间��_�Ђ̂��Ƃ��낤�D����ˏ���ˎ�e��������Ր_�D
"����Ɍ����Ă���܂��͘e��l�̂��{�ŁA���̉��ɔ��Ǒ���̂����~������"�i������j |
����_�� |
 |
2017 |
| �ɕ��̓n�� |
���ڂ���̂킽�� |
������i�s�X��(1890)�j |
���̎s |
�w�����ɏo���u������v�̎�l�������Y�́C�K�ې�̓n����ɉ����Ă����e�̋w�ɏo���킷�D�K�ې�ɂ͏㉺�Q�̓n�����������D���싴�̂Ƃ��낪���̓n���C�l�����̈����̂Ƃ��낪��̓n���D���̕���́C��ɋ߂���̓n�����낤�D���ɓo��Ə邪�������D
"�o�ĎQ��܂����Ƃ���͔d�B����ɕ��̓n��ł������܂�"�i������j |
��̓n���� |
 |
2017 |
| ���� |
����͂� |
�^����(�p�앶��01:10)�Ȃ� 2��1�� (����2��) |
�ԕ�S��S�� |
�ԏ����S�͏��R�����`�����E�Q���C�d���ɉ���D�ԏ����̋��_������ƓV�������q�E�p���肪���т����D�����ƈ�o�̋ʐ�́C�u�^���ԁv������炵����������X�p�C�X�I�n���D
"��ꂱ���́A�d�B�����̏��A�ԏ����S"�i�^���ԁj |
�����隬��]�� |
 |
1999 |
| �ԕ� |
������ |
���ܘY(�u���a��O6:26) �Ȃ� 22��13�� (����3��, ����16��, ���3��) |
�ԕ�s |
�d�B�ԕ�ܖ��O��D���ƘV�Ƃ�������ԕ�l�߂̑启�R�ǔV���C����̋}�ɐڂ��č]�˂삯���邪�C�ԓ��̗g���������������Ƃ���ɔ����a�͐ؕ��D�x���肵�R�ǔV���D
"�R�ǔV���Ă����̂͂ˁA�d�B�ԕ䂩��ˁA���n�Ŕ���ė����"�i���ܘY�j |
�ԕ�ˑ�Γ@������ |
 |
2016 |
| �Ԋx�� |
�������� |
��v�ۑ\��_�U�w���i�S�ԉ� (1889)�j |
�ԕ�s������1992 |
�����@��_�R�Ԋx���D���ƕ�D�q�ϗL���D�l�\���m�̕�C�ؑ��̂ق��C��Ζ��c�̏��C�{��������V��̌Ղ̖n�G������D�����ɁC���������𒆐S�ɁC��ΐe�q�C�l�\���m�̕悪����ł���D���ɂ͋`�m�̈┯�����߂��Ă���Ɠ`����D
"����͉Ԋx���Ɖ]���ē������܂̌�����c�c�G�[���ԏO�����ĎQ�w�v���������ǂ�����ē����肢�Ƃ�������܂�"�i��v�ۑ\��_�U�w���j |
�Ԋx�����Ɨ�_ |
 |
2016 |
| �Ԋx��:�l�\���m�̕� |
�����イ�������̂͂� |
��v�ۑ\��_�U�w���i�S�ԉ� (1889)�j |
�ԕ�s������1992 |
�Ԋx���ɂ́C������������͂�ŁC�ԕ�Q�m�l�\���m�̕悪����D
"���ꂩ���Ԃ��l�\���m�̕�ֈē����������܂���"�i��v�ۑ\��_�U�w���j |
���������E�l�\���m�� |
 |
2016 |
| �ԕ�� |
���������傤 |
�ŋ����C(���l����05:25)�Ȃ� 2��2�� (����1��, ���1��) |
�ԕ�s�㉼�� |
���\14�i1701�j�N�C�]�ˏ�ł̐�����������̋g�Ǐ���ւ̐n���ɂ�肨�ƒf��ƂȂ�D�ԕ��̈�\�͂قƂ�ǂȂ��D������Č����ꂽ���́D
"�ԕ�̏�̖����n������G����������܂ł�䅓�h��"�i�ŋ����C�j |
�ԕ����� |
 |
2016 |
| ���̍` |
�ނ�݂̂Ȃ� |
���ɑD(�n���Ē�5:02) 1��1�� (���1��) |
���̎s��Ò����� |
���Ð猬�Ƃ���ꂽ�ɉȍ`�D�u�d�B����v�̈�s�������ʼn��D�����D���ł͋����Ώ������ۑ��ł���قǂ̖K��s�ւȉ��u�n�D
"�A��͑D�Ŕd�B�̎��̍`�֏オ��܂��āA���ꂩ��P�H����������"�i���ɑD�j |
���̒� |
 |
1999 |
| �Ԋ� |
���ڂ� |
������i�s�X��(1890)�j |
�P�H�s�Ԋ��� |
�u������v�̏I�ՁC�D�����������n���D�́C�K�ې�������ė��삩��Ԋ��܂ŗ���Ă��܂��Ƃ̋q�̃Z���t�D�Ԋ��́C�ۋT�˂Ɨ���˂ɂ���ĕ����x�z����Ă���C�����́C���˂̋��E�ɉ˂����Ă����D
"���̂܂܂őł�������Ă����Ă͖Ԋ��܂ʼn����b�Ă��܂ӂ�"�i������j |
���� |
 |
2017 |
| �����` |
�����܂��� |
���ق���(�n���Ē�6:15) 1��1�� (���1��) |
�P�H�s |
�]�ˊ��ɕP�H�s�X�Ƃ̊Ԃ̐��H���������ꂽ�D�H��p�n�̖������i�ށD
"�����̍`�̉�D�≮�ŒW�H���⑾�Y�Ƃ����傫�ȉ�"�i���ق����j |
�����` |
 |
1999 |
| �P�H |
�Ђ߂� |
���ɑD(�n���Ē�5:02)�Ȃ� 26��12�� (����13��, ���13��) |
�P�H�s |
�P�H�ƌ����Δd�B�M���~�D���e�_�Ђ͏\�_�Ёi�P�H�s�\�O���j���D�M���~�̂��e�̗���J��D�e�̌�䂪���Ă���̂̓V�����H
"�d�B�̎��̍`�֏オ��܂��āA���ꂩ��P�H���������āA�d�B�H�𓌂֓���"�i���ɑD�j |
���e�_�� |
 |
2012 |
| �P�H:���� |
�����܂� |
�E�������ꉮ��k�i����, 9�� (1892)�j |
�P�H�s���� |
�P�H�s�X�̐����ɁC���݂������̖����c��D�P�H����O�傪���������Ƃ�������Ă����D�ۂ��̂��b�ŁC���̒��ׂ��̂������𗯂߂鉄�D����������v���J�ŁC�����͒n���Pm�ɖ��܂��Ă���Ƃ����D
"�d�B�P�H�̏鉺�����̗�����"�i�E�������ꉮ��k�j |
���O�勴�� |
 |
2017 |
| �P�H:���� |
�ӂ��� |
���݂Ȃ�ٓ̕�(�����Ε���2:04) 1��1�� (���1��) |
�P�H�s������ |
�P�H�s���̕��������낤�D�ٌc�̓`�L�ŁC�u�䏊���x��铢�ٌc��g�̒i�v�̐����D�{�w�̖��ƌ����߂������C���������ċS��ۂ��������낤�Ƃ������C�����Ƃ߂�����������Č���̏؋��ƂȂ�D�ٌc�͂��̂Ƃ�������x�C�����͐��U�����̂܂܁D�u�ٌc�Ə����͔n�����ȃ@�m�@�v�D
"�d�B���ʎR�̒t���ŋS��ہA�\�Z�̂Ƃ��A�P�H�ߍݕ��䑺�{�w�̖^�Ƃ����h���ւ����āA���܂荇�킹�܂�"�i���݂Ȃ�ٓ̕��j |
�������̒����W |
 |
1999 |
| �P�H�� |
�Ђ߂����傤 |
�M���~(�u���a��O4:25)�Ȃ� 3��1�� (����1��, ���2��) |
�P�H�s�{�� |
���ÎR�쉀�̓W�]��͕P�H��\�i�̈�D���_�����n�ɕP�H�o�g�̎O��ڌj�Ē��̕悪����D�ォ�猩���"��"�̎��̐̔z�u�D���̂Q�Ɏl�G�̔o�傪���܂�Ă���D
"�P�H��鉺�ɏZ��ł��Ȃ���A�M���~�m��˂����イ�����������"�i�M���~�j |
�P�H�� |
 |
2017 |
| �P�H��:�V�� |
�� |
�M���~(�u���a��O4:25) 2��1�� (����2��) |
�P�H�s�{�� |
����P�H��{�ہC�ܑw�̑�V��t�D���e���݂���ɂ�������˂��C�P�H����ɂ���D���E������Y�̗v���̈ꕔ�D
"�ԉ��~�m��Ȃ������炨�V��m��˂��悤�Ȃ��̂�"�i�M���~�j |
�P�H��V��Ƃ��e��ˋʊ_ |
 |
1999 |
| �P�H��:���e�̈�� |
�������̂��� |
�M���~(����܂�ȁC�V���o�� (2010)) |
�P�H�s�{�� |
�P�H���R���ȗւɂ����ˁD���Ԃ�ʂ��Ē����̂����ƁC�����Č�����̂͐��ł͂Ȃ��R�C���D�����������邪�C�������炨�e�������̂��낤�D�M���~�͕P�H�鉺�̉�ꂩ�������~�C���e�̕�͏�̓��̌܌��@�ɂ������Ƃ�������C�P�H����̂��Ƃł͂Ȃ������D
"�P�H�ɂ͍����u���e�̈�ˁv�����邻����"�i�M���~�j |
�P�H�邨�e�� |
 |
2017 |
| �M���~ |
����₵�� |
�ꕶ�ɂ���(����10:08)�Ȃ� 13��3�� (����8��, ���5��) |
�P�H�s:�ˋ� |
���e�̗H�삪��Ȗ�Ȍ����Ƃ������C�ǂ������ꏊ���킩��Ȃ������D
"�d�B�M���~�S�R�ق̒i"�i�ꕶ�ɂ��݁j |
�@ |
�@ |
�@ |
| �ԉ��~ |
����܂₵�� |
�M���~(�u���a��O4:25)�Ȃ� 6��1�� (����3��, ���3��) |
�P�H�s:�ˋ� |
�M���~�̕ʖ��D
"���O��̎ԉ��~�m��˂����i�����j���̎ԉ��~���M���~��"�i�M���~�j |
�@ |
�@ |
�@ |
| �s�� |
�������� |
���k�s���i�j�Ē��R���N�V���� 5, �}�����[ (2003)�j�Ȃ� 2��1�� (���2��) |
���Ɍ� |
���Ɍ�������여���C�P�H�s�����֒����D�u���ɑD�v�̐�s�����Ɓu���k�s���v�̕���D�y��̏�Ō�H�ɗ����Ԃꂽ�]�ː߂������z�㉮���Y���q���a��E���D�]�ːl��ł́C�˓c�̐쌴������ɂȂ�D
"�P�H�̓��𗬂�Ă���܂��s��̒�ւ������Ă������ɂ́A���͐��̂ق��X���Ă���܂�"�i���k�s���j |
�s��� |
 |
2019 |
| �䒅 |
�����Ⴍ |
���k�s���i�j�Ē��R���N�V���� 5, �}�����[ (2003)�j |
�P�H�s�䍑�쒬�䒅������ |
�䒅�i�����Ⴍ�j�D�u���k�s���v�ɏo�Ă���D�P�H�Ɖ��Ð�̊Ԃ̏h�D�{�w�Ղ͌���C�d���������ɂ͓����̑b���c��D
"�����Ƃ��Ă������܂��Č䒅�Ƃ��������������܂�"�i���k�s���j |
�d�������� |
 |
2004 |
| �]���̓V�_ |
���˂̂Ă� |
�d�B����(�O����2:06) 1��1�� (���1��) |
�����s�]�����]��2286-1 |
�]���V���_�ЁD�R�z�]���w����k�������D�������疾���o�ĕ��ɂɂ����āC�u�d�B����v�̖����������D
"�]���̓V�_���Q�w�������܂��Ė���������Ԃ�Ȃ������������܂���"�i�d�B����j |
�@ |
�@ |
�@ |
| �]���̏� |
���˂̂܂� |
�d�B����(�����12:1) 1��1�� (���1��) |
�����s�]�����]��2286-1 |
�]���V�����D�������ɕ{�z���̍ۂɏ���A�����Ƃ����D���ܑ͌�ځD�͎��������͗쏼�a���ɕۑ�����Ă���D
"�d�B�́A���̖����̑������ł������܂��B����̏��ɑ]���̏�"�i�d�B����j |
�]���V�_�Ƒ]���̏� |
 |
1999 |
| �̕�a |
�����̂ق��ł� |
�d�B����(�u�����吳6:06) �Ȃ� 4��1�� (����2��, ���2��) |
�����s����ɒ�����171 |
���ΐ_�Ђ̌�_�̂̋��D�T�C�R���^�ň��������ɔ�яo�Ă���D��a�w������������Ȃ����C�K���|�C���g�D�܂��Ƀ~�X�e���[�X�|�b�g�D
"����̏��A�̕�a�Ȃnj����������āA�{���A���̕��ւ�����܂���"�i�d�B����j |
�̕�a |
 |
1999 |
| ���� |
�������� |
�Ԕ�(�n���Ē�1:20)�Ȃ� 17��8�� (����16��, ���1��) |
�����s |
�u������v�̗w��u�Ԕ��v�̑��o���s�n�D�����_�Ёi�������j���ӂ́C���Ð쐅�^�̖x�ƒ����݂��c��D
"���o����Ă���Ƃ͌���Ȃ�Ƃ��A�����܂ő̂��^��ł��낤�āA�y�U����ȂƂ����"�i�Ԕ��j |
�����_�� |
 |
1999 |
| �����̏� |
���������̂܂� |
�d�B����(�O����2:06)�Ȃ� 2��2�� (���2��) |
�����s���������{��190 |
�����_�Г��ɏ�����X�����A�����Ă���D�����ɂ͎͌����������̏����W������Ă����D
"�d�B�֓���܂��Ƃ����͂܂����̖��������̏�"�i�d�B����j |
�����̏� |
 |
1999 |
| �����̏� |
���������̂܂� |
��i��(����07:01)�Ȃ� 13��7�� (����11��, ���2��) |
�����s�������Ȃ� |
�����̏������̏��̂悤�Ȏ��Y�����̂������D
"�����ɑ����̏������߂ł����肯��"�i��i�ځj |
�@ |
�@ |
�@ |
| ���� |
�������� |
���ɑD(�O����2:09)�Ȃ� 2��1�� (���2��) |
����s |
��s�����œo�ꂷ��D���Ð�́C���Ð�s����여����D���Ð�ƌ����Γ��{�ѐD�i�j�b�P�j�D�Б�Q�����̂܂c�钬���݂͋}���Ɏ�������D
"�d�B�̉��Ð삾��"�i���ɑD�j |
���� |
 |
2012 |
| �ԕǖ��_ |
�������ׂ݂傤���� |
�L��(����08:10) 1��1�� (����1��) |
���Ð�s���Ð쒬�{�� |
���Ð�̏t���_�Г��ɂ���ۋT�_�Ђ��ԕǂł��邱�Ƃ���̑��́D�����L�`��������C�f���u�k�ɂ��Ȃ����D�_�Ђɏ����ꂽ�R���ɂ��ƁC�u�L��v�Ƃ��Ȃ��悤�Șb�D�����D���̖��E�l�̎����Ă���l�R���C�T�C�R���̖ڂ���Œm�点���D�A�蓹�ɐE�l�͎E����C�ނ̃l�R���Ԃ蓢���ɂ����D���̌��Ő��܂����ǂ��Ƃ����D�܂������ʕ������C�P�H��̓V����J���Ă���Y�����_�i���ǕP�Ƃ��D�������ׂ݂傤����j�̐��̂͗d�ςŁC���Ɏp���������Ƃ����D
"�L��������b��S���߂��Ƃ����c�c�ԕǖ��_�̔L�Ƃ��A���邢�͓瓇�̔L"�i�L��j |
�ԕǖ��_ |
 |
2012 |
| ����̏� |
���̂��̂܂� |
������(�����l����05:07) �Ȃ� 5��3�� (����2��, ���3��) |
���Ð�s���㒬���c518 |
���Ð�s�̔���_�Г��ɂ��鑊���̏��̂��ƁD����̔���̏��́C�j���Ə������r���ł킩�ꂽ�����ŁC�w�ȁu�����v�ɗw����D�蕶�ɂ���V�R�L�O���w�肳�ꂽ�̂͂R��ڂ̏��D���݂͂T��ڂ̏��D
"�w�����̔���̏����N�o��āx�Ƃ���"�i������j |
����̏� |
 |
1999 |
| ����̏� |
���̂��̂��� |
�d�B����(�O����2:06) �Ȃ� 2��1�� (����1��, ���1��) |
���Ð�s���㒬���c518 |
����_�Ђ̕D�ق����肵�����N���ŁC���d���D������悤�ɂ��Ă���Ă���̂͂��肪�����D
"����̏��ɂ͑]���̓V�_���Q�w�������܂���"�i�d�B����j |
����̏� |
 |
1999 |
| �薍�̏� |
�Ă܂���̂܂� |
�d�B����(�O����2:06)�Ȃ� 2��1�� (���2��) |
���Ð�s�ʕ{���� |
�d�B���̖�������̈�D�ʕ{�i�ׂӁj�̏Z�g�_�ЎБO�D�߂��ɔ엿�ŋN�Ƃ������؊w���̓����萼�m�ق�����D�m�炸�Ɍ������ēx�̂��ꂽ�ٗe�D
"�̕�a�A�ʕ{�薍�̏�"�i�d�B����j |
�薍�̏� |
 |
1999 |
| �d���� |
�͂�܂Ȃ� |
�d�B����(�u�����吳6:06) �Ȃ� 2��1�� (����2��) |
���˓��C���� |
�d���C�W�H���C���쌧�������Ɉ͂܂��C��D
"��������U������Č��ȁA���Ɍ�����̂��d���傾"�i�d�B����j |
�@ |
�@ |
�@ |
| �W�H�� |
���킶���� |
������(������1:05) �Ȃ� 30��18�� (����19��, ���11��) |
�F�{�s�C�O���S |
���˓��C�ɕ����ԁC���{��U�ʂ̖ʐς������D�^�}�l�M�C�l�`�ŋ����L���D2017�N�ɒW�H�����ނƂ���C�j���}��̊G�{����R�����o�ł���Ă���D�_�b��^�}�l�M���e�[�}�ɂȂ��Ă���D�ʐ^�̂��̂��듇�_�Ђ́C�C�U�i�M�C�U�i�~������̒n�Ƃ����D
"������Ƃ��ɏo�Ŏ��́A�g�̒W�H�̓�������"�i������j |
���̂��듇�_�В��� |
 |
2007 |
| �≮�̒[ |
�����̂͂� |
�d�B����(�O����2:06)�Ȃ� 2��2�� (���2��) |
�W�H�s�≮ |
�W�H���k�[�̍`���D�����炽���t�F���[�ōs�����i2010�N�ɂ͎����p�~�j�D�����͂��Ȃ������Ă̌��i�m�ԁj�D�≮�ɂ͉�����C�G���͌i���n�D
"����͒W�H�̊≮�̒[��"�i�d�B����j |
�G�� |
 |
2007 |
| �ɜQ���_�{ |
�����Ȃ����� |
�Î��L�k�i���Ə���������p�u�Ă����Ɓv 3, �Ă����Ƃ̉� (2015)�j |
�W�H�s����740 |
�W�H����V�{�D�Ր_�́C�ɜQ�����ƈɜQ�f���D���̒��ŁC������_�b�Ƃ��ēo�ꂷ��D�����݂��I�����ɜQ�������C�W�H���̗H�{�ɒ��܂����Ɠ`����D�����ɂ͎���800�N��������v�w�̓킪����D�����C�����̎Q�q�q�łɂ�����Ă����D
"�ɜQ���_�{���т��܂�"�i�Î��L�k�j |
�ɜQ���_�{ |
 |
2020 |
| �F�{ |
������ |
�_�������A���}�W��(�����������:2) 1��1�� (���1��) |
�F�{�s |
�ȉ��R���C��������̐V��P��ɏo�Ă���n���������D�F�{��ɂ́C���ږx�����ɐ���ł����ʼnE�q��K���K������D�l�Ԃɉ����C�C��n���Ďŋ��������y����ł����D�����̕��ł́C�����̗t���D�Ɍ��������Č������Ă���q�ɋC�Â����D����͂��₵���ƁC���������������Ƃ���C�K�͐H���E����Ă��܂����Ƃ����D���₢��C��͂̂���K������C�����Ƃ��̌���C�ŋ������̓ޗ����V�䗠�ɂЂ���ŁC�D���Ȏŋ������Ă����ɈႢ�Ȃ��D�����ł��ʼnE�q��K���J���Ă������C�F�{�̖K�⎞�͏��|�V�쌀�̛�������Ă����D2002�N�ɒ������Ď������Ƃ��ɂ́C�������܂��Ă���C���łɂӂ邳�Ƃɖ߂��Ă����̂��낤�D
"�F�{�āc�c���́A�W�H���̏F�{������"�i�_�������A���}�W���j |
�F�{��@�ʼnE�q��K |
 |
2007 |
| �R�� |
��� |
�σP���i���Ə���������p�u�Ă����Ɓv 36, �Ă����Ƃ̉� (2019)�j |
�F�{�s�R�ǂ����� |
�I�W�C�����ɂ�ތR���I�v�ՂŁC���ΎR�ɂ͖������ɖC�䂪�z���ꂽ�D���C���28cm�֒e�C�́C�����ő�̉ΖC�ŁC�����U���ɂ������D
"�����̖����A�W�H�̗R�ǂɎ���Ԃɂ���܂���A�����A��k�ꗢ���̓��əт��܂���"�i�σP���j |
�R�Ǒ��C�� |
 |
2020 |
| �����L�[�Z���^�[ |
���[���[ |
�_�������A���}�W��(�����������:2) 1��1�� (���1��) |
�F�{�s���c289 |
�W�H����݁C���勽�ƂȂ�Ԋό��n�D�쐶�U��200�����a�t�����Ă���D������������ʂ�o�X�͓��ɂR�{�D�ԂŖK���l���s���ɂȂ�Ȃ��悤�C���x�����x���ē��Ŕ��������T���������D���قƃZ�b�g�ɂȂ������勽���C�Ȃ��Ȃ��Ƒ��A��ɂ̓n�[�h���������D�i�]�̃p���_�C�X�I
"����̉Ԃ��炫����Ă��ł���B�����L�[�Z���^�[�����Ƌ߂�����"�i�_�������A���}�W���j |
�����L�[�Z���^�[ |
 |
2007 |
| �W�쒬 |
����Ȃ傤 |
�_�������A���}�W��(�����������:2) 1��1�� (���1��) |
�삠�킶�s |
���O���S��W���i�Ȃ傤�j�D�W�H���암�D���̎�l���͂���������֒ʋ̓��X�𑗂�D2005�N�C�����ɂ���W���͏��ł����D�����ق̕ǖʂɂ͋����͂�������D
"�W�H���́u�W���v�������Ɂu��v�Ə����āu�W�쒬�v"�i�_�������A���}�W���j |
��W������ |
 |
2007 |
| ���� |
�ʂ��� |
�Î��L�k�i���Ə���������p�u�Ă����Ɓv 3, �Ă����Ƃ̉� (2015)�j |
�삠�킶�s���� |
������_�b�D�W�H���̓�ɏ���������D�I�m�S�����̃��f���Ƃ̐����D�ʐςR�����L�����܂�D�G�X�q��̂悤�ł��C�����ȓ��ł��Ȃ��D�����̊�ʁC�㗧�_��́C�ق�Ƃ��ɉG�X�q�̂悤�ȏ����ȓ��ŁC��͂荑����_�b���`���D
"�W�H���̋߂��ɂ���<����>�Ƃ����A�G�X�q��̂悤�ȏ����ȓ�������܂����A���ꂪ<�I�m�S����>�̃��f����������"�i�Î��L�k�j |
���� |
 |
2020 |
| �|�푺 |
�䂰�ނ� |
����(��������1:05) 1��1�� (���1��) |
�s�� |
�|�퓹�����C�O�g�̍��|�푺�̏o�g�Ƃ���D�s���D�����́C���ʂ͉͓��̍������̏o�g�Ƃ����D�����傫�������̂��Ƃ����ƃi�j�ŁD����ō��������낤�Ƃ����̂�����X�S���D�����łȂ��Ă������Γ��C�������i���E�ԁj�D
"�킪���ł͋|�퓹���Ƃ����l��������傫�����������ŁA����͒O�g���|�푺�̐��܂������Ɛ\���܂�"�i�����j |
�@ |
�@ |
�@ |
 ���Ɍ�
���Ɍ� 

 �����n���}��
�����n���}��