| 地点名 |
この1題・登場回数 |
位 置 |
備 考 |
写真と撮影年 |
| 山梨県 |
やまなしけん |
鰍沢(講明治大正7:37) など 11件5題 (東京11件) |
山梨県 |
滑稽落語に出てくることは少ないが,山梨県はいくつかの人情噺の舞台に取られている.県東部から出発し,甲府から身延へと富士川を下り,富士山をひとめぐりするルートで落語地名を紹介する.
「鰍沢」や「いが栗」では,甲州の山中で旅人が道に迷う.小室山で毒消しの護符を授かった後,「鰍沢」の主人公は雪の中で道に迷って殺されかける.小室山の裏道を歩いていたら,写真のように道が崩れており,あやうく谷底に滑り落ちそうになったことがある.
"今は山梨県と申しますが、中々山有県で"(鰍沢) |
鰍沢への山道 |
 |
2014 |
| 甲斐 |
かい |
いが栗(騒人名作04:18) など 46件25題 (圓朝5件, 東京35件, 上方6件) |
山梨県 |
旧国名.亡者となって娘を呪う「いが栗」の怪僧が現れるのは,甲州の山中に設定されていることが多い.甲斐国は,水晶,印伝,甲斐絹,アワビの煮貝,ほうとうなどが古くからの特産物.途絶えてしまった甲斐絹の技術を復活させようと頑張っている.富士急創立50周年を記念して,1976年に発行された記念切符は,甲斐絹織の技術を駆使して作られた労作.7000本もの糸が使われているという.デザインは真鍋博,題字は富士吉田市長石原茂の揮毫になる.
"ある旅人が甲州の山中へ入って道を踏み迷い、人に尋ねたくも樵夫一人通りません"(いが栗) |
甲斐絹織の記念乗車券 |
 |
2022 |
| 郡内 |
ぐんない |
沢村田之紀(不二演藝画報復刻:13) 1件1題 (東京1件) |
山梨県 |
山梨県の東部."甲斐絹のパッチ"でも使われる絹織物の産地で,かつては大いに栄えた土地だった.小仏峠にウワバミが出るバージョンでの「たのきゅう」の公演先になる.なお,郡内縞の夜具布団など用例はカウントしなかった.
"この夏休みの間、郡内から買いに来ているので"(沢村田之紀) |
郡内縞ランチョンマット |
 |
2022 |
| 上野原 |
うえのはら |
沢村田之紀(不二演藝画報復刻:13) 1件1題 (東京1件) |
上野原市 |
河岸段丘の"上の原".段丘下の上野原駅から,急坂を上って本来の町へ入る.宿として残るのは本陣跡ぐらい.天然記念物の大ケヤキの町をうたっている.前項,郡内地方の中心地.
"上野原から八王子へ乗り込むこととなり"(沢村田之紀) |
上野原宿本陣の門 |
 |
2004 |
| 野田尻 |
のだじり |
鼠小僧闇路初旅(にっかつ談志:4) 1件1題 (東京1件) |
上野原市野田尻 |
甲州街道の宿.上野原発のバス終点からさらに徒歩.本陣跡などが表示されている.次の宿の犬目までは歩いて行くしかないが,途中には座頭転ばしと呼ばれる難所があった.
"野田尻ぢゃァ、庄屋の檀那寺へ火を掛けて祠堂金を盗みだした"(鼠小僧闇路初旅) |
西光寺裏の旧甲州街道 |
 |
1999 |
| 犬目 |
いぬめ |
鰍沢(講明治大正7:37) など 5件2題 (東京5件) |
上野原市犬目 |
「鰍沢」で身延参りの主人公が,雪に道を迷い尋ねるのが犬目(いぬめ)の方向.読みの似た伊沼(いぬま,別項)の方が身延山に近いが,特に伊沼と改める理由もない.鉄道からはずれて閑散とした甲州街道犬目宿には,中央線四方津(しおつ)からのバスも日に数本しか来ない.
"ここから犬目へはどう出ましてよろしゅうございますかナ。そうですネ、どちらへ行ってよいのですか分かりません"(鰍沢) |
犬目バス停 |
 |
1999 |
| 猿橋 |
さるはし |
駅名読み込み川柳大会(牧野駅名:1) 1件1題 (東京1件) |
大月市猿橋町猿橋 |
十二支のつく駅名,猿橋駅.1902年の開業時は,"えんきょう"と称した.もちろん,日本三奇橋の一つの猿橋に由来する.深い谷をまたいでいるため,橋脚がない.両側から猿が手を伸ばしたような刎木がのびてつながっている.再建して現存する.
"猿橋は猿が渡った蔓の夢"(駅名読み込み川柳大会) |
猿橋 |
 |
2024 |
| 大月 |
おおつき |
猫の皿(大日本図書館10:02) 1件1題 (東京1件) |
大月市 |
大月駅からひときわ目立つ岩殿山は,戦国期武田勝頼家臣の小山田信有の山城.内通により滅ぼされた.上まで登ることができる.「猫の皿」の茶店は,普通は熊谷先の石原で演じられる.
"これから、大月にかかろうという小さな茶店でひと休み"(猫の皿) |
岩殿城址 |
 |
2008 |
| 花咲 |
はなさき |
五人小僧噂の白浪(大川屋 (1892)) |
大月市花咲 |
甲州街道下花咲宿と上花咲宿が隣接していた.下花咲宿本陣跡の前に,明治天皇花咲御小休所碑と本陣碑がならんでいる.建物は国重文で,明治13年に明治天皇が休まれた上段の間も保存されている.
"花咲初狩篠子駒飼勝沼栗原等の宿々に寄って"(五人小僧噂の白浪) |
下花咲宿本陣跡 |
 |
2019 |
| 初狩 |
はつかり |
鼠小僧闇路初旅(にっかつ談志:4) 1件1題 (東京1件) |
大月市初狩町中初狩,下初狩 |
初狩小学校前の歩道橋下に芭蕉句碑 葎塚がある."山賤の頤とつる葎哉"(やまがつのおとがひとづるむぐらかな).初狩駅は,かつてスイッチバック駅で,踏切もない名残の貨物用配線を越えて改札口に向かう.
"勝沼、初狩、浅川、と、破った土蔵は数知れず"(鼠小僧闇路初旅) |
芭蕉句碑 葎塚 |
 |
2008 |
| 篠子 |
ささご |
五人小僧噂の白浪(大川屋 (1892)) |
大月市笹子 |
笹子(ささご).甲州街道黒野田宿.明治36年に笹子トンネルが開通したことにより,笹子駅が開業した.峠の力餅として売られていた笹子餅が,明治38年に駅売りされるようになった.粒あんの入ったよもぎ餅で,パッケージには峠の東にあった矢立の杉が描かれている.今は,駅そばの店舗で買える.
"花咲初狩篠子駒飼勝沼栗原等の宿々に寄って"(五人小僧噂の白浪) |
笹子餅 |
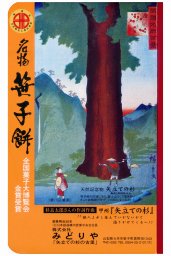 |
2019 |
| 笹子峠 |
ささごとうげ |
無精風呂(国書レコード:48) など 2件2題 (圓朝1件, 東京1件) |
大月市〜甲州市 |
甲州街道の難所.標高1096m.現在は国道の笹子トンネル・新笹子トンネルが開通し,この古い隧道も用を終えた.さらにこの上を旧道は通っている.矢立の杉は,戦勝を願った戦死が矢を射かけたという.上部が折れて,中は空洞となっている.
"暗いとも、夜も十二時過ぎると狼が出るゾ。笹子峠だねまるで"(無精風呂) |
笹子隧道 |
 |
1998 |
| 駒飼 |
こまがい |
五人小僧噂の白浪(大川屋 (1892)) |
甲州市大和町日影 |
甲州街道駒飼宿.笹子峠の西側にあたる.本陣と脇本陣の建物もなくない,残念ながら標柱しかない.宿の北に,馬蹄の跡が刻まれた巨大な駒飼石があったが,水害のあと,たたき割られた.残欠に彫られた芭蕉句碑が再建されている,"秣負ふ人を栞の夏野哉".諏訪神社の鳥居の脇に,駒飼石らしい石が置かれていたが,特に説明はなかった.
"花咲初狩篠子駒飼勝沼栗原等の宿々に寄って"(五人小僧噂の白浪) |
駒飼宿脇本陣跡 |
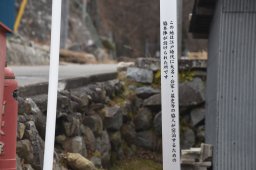 |
2019 |
| 初鹿野 |
はじかの |
鼠小僧闇路初旅(にっかつ談志:4) 1件1題 (東京1件) |
甲州市大和町初鹿野 |
初鹿野の駅名は甲斐大和になってしまった.バス停も近いので高速バスで行くのも面白い.
"此の先、初鹿野まで参りますにも、金が頼り"(鼠小僧闇路初旅) |
初鹿野を望む |
 |
1998 |
| 天目山 |
てんもくざん |
真田小僧(講明治大正3:53) など 10件2題 (東京10件) |
甲州市大和町木賊 |
天正10(1582)年3月,天目山の戦により,武田氏は滅亡した.敗走する武田勝頼らは,菩提寺の天目山栖雲寺を目指したが,その途中ではさみ撃ちにあい,武田勝頼,信勝親子は田野の地で自刃した.その地が現在の景徳院になる.境内には武田勝頼らの五輪塔や,武田勝頼生害石がある.天目山へは,夏場は甲斐大和駅から大菩薩峠への登山客向けのバスが利用できる.途中には,家臣の土屋惣蔵こと土屋昌恒は,崖の蔦につかまって,織田勢を食い止めた片手千人斬りの地や,小宮山内膳が奮戦した鳥居畑古戦場などがある.「真田小僧」では,真田幸村は大阪城から薩摩へ落ちたという.
"なんでも武田勝頼が、天目山で討ち死にをした時なんだ"(真田小僧) |
武田勝頼生害石 |
 |
2024 |
| 大菩薩峠 |
だいぼさつとうげ |
大久保曾我誉廼仇討(百花園, 1-13 (1889))など1件1題 (東京1件) |
塩山市〜北都留郡小菅村 |
甲州の裏街道,小菅村と塩山をつなぐ標高1897mの峠.中里介山の大河小説『大菩薩峠』で,行ったことがなくても名前は聞き覚えのある地名.江戸期の峠は,現在大菩薩峠の標柱が立っているところではなく,賽ノ河原と呼ばれる鞍部だったという.そこから西側へ下る旧道登山路も残っている.用例にある大河内は奥多摩の小河内(おごうち),猿山村は山梨県の塩山(えんざん)のこと.
"大河内より大菩薩を越え八里の峠を越して猿山村へ出ました"(大久保曾我誉廼仇討) |
大菩薩峠を望む |
 |
2024 |
| 川浦村 |
かわうらむら |
吾妻の猪買い(定本 九州吹戻し, 新人物往来社(2001)) |
山梨市三富川浦 |
秩父まで猪肉を買いに行く「吾妻の猪買い」(池田の猪買い)の道中付けで,秩父を抜けると川浦へ出るとの説明.塩山から雁坂峠をこえて秩父に通じる雁坂街道の要所として,永徳4(1382)年には関所が設けられたという.川浦口留番所の番屋と門は,1994年に復元された.
"雁坂峠を越えて行くと甲斐国山梨郡川浦村へ出る重要な場所でございます"(吾妻の猪買い) |
川浦口留番所 |
 |
2008 |
| 清里 |
きよさと |
死に神remix(京極噺六儀集, ぴあ (2005)) |
北杜市高根町清里あたり |
清里町は北海道にあるが,ペンションの清里として高根町の清里の知名度の方が抜群.今は北杜市となったが,謂われがないため知名度ゼロ.それが証拠に誰も読めない.再び北海道北斗市とバッティングしてしまった.写真は清里の象徴とも言える清泉寮を運営するKEEP協会創始者,ポール・ラッシュ[1897-1979]の銅像.
"最初は、これでもしあわせ亭夢八という、清里のペンションのような名前を名乗っておったのでございます"(死に神remix) |
清泉寮ポール・ラッシュ像 |
 |
2008 |
| 若神子 |
わかかみこ |
侠客 業平文治(時事新報 (1927)) |
北杜市須玉町若神子 |
若神子(わかみこ).談洲楼燕枝(2)が演じたとされる「業平文治」の一節.圓朝オリジナルとは全く違う筋立てのため,圓朝ものとして扱わなかった.噺の終盤で,興津から上陸した文治が,妻の待つ前橋へ向かう道中付け.若神子は,佐久往還の宿場の一つで,写真のような旧家がぽつぽつと残っている.
"甲府へ行ちやァ廻り道だから韮崎へ抜けて、穂足から若神子"(侠客 業平文治) |
若神子の旧家 |
 |
2024 |
| 韮崎 |
にらさき |
侠客小金井桜(毎日新聞 (1898)) |
韮崎市 |
韮崎の窟観音は,七里岩と呼ばれる長い崖の南端にあたる.八ヶ岳の岩砕流が30キロにわたって堆積している.窟観音は洞窟になっていて,向こう側へぬけることができた.上に登ると白亜の平和観音.見下ろせば,町のランドマークだったアメリカヤが見える.このあたりの店は,宴会とならんで無尽に使えますとの看板が目立った.山梨県には資金を相互扶助する無尽の習慣が残っている.「三人旅」の連中は,無尽にあたった金で伊勢詣りに出発するのが発端部になる.
"浅五郎は先頃より韮崎の馬市場へ、賭博の稼ぎに出向きしと"(侠客小金井桜) |
韮崎窟観音 |
 |
2019 |
| 塩山 |
えんざん |
五人小僧噂の白浪(大川屋 (1892)) |
甲州市塩山 |
旧塩山市の北西部にある歌枕の塩ノ山が塩山の地名の由来.塩が取れたのではなく,四方からよく目立つ山とのこと.甘草屋敷,塩山温泉,ころ柿が名物.甘草栽培で財をなした甘草屋敷は塩山駅のすぐ北にある.
"ハイ私は塩山の者でございすが"(五人小僧噂の白浪) |
塩ノ山 |
 |
2019 |
| 勝沼 |
かつぬま |
鼠小僧闇路初旅(にっかつ談志:4) 1件1題 (東京1件) |
甲州市勝沼 |
旧東山梨郡勝沼町.市街は勝沼ぶどう郷駅から離れている.一人で乗るには恥ずかしいブドウ型の観光用バスが連絡している.甲州ワインの中心地で,どこもかしこもブドウ畑.
"勝沼、初狩、浅川、と、破った土蔵は数知れず"(鼠小僧闇路初旅) |
勝沼市街を望む |
 |
2008 |
| 栗原 |
くりはら |
五人小僧噂の白浪(大川屋 (1892)) |
山梨市上栗原, 下栗原 |
栗原(くりばら).甲州街道栗原宿.栗原山大翁寺の周囲は,この地を支配した栗原氏の屋敷跡だった.大翁寺の西にある大宮五所大神の拝殿部分は,歌舞伎舞台になっている.山梨市駅からコミュニティバスが走っている.
"花咲初狩篠子駒飼勝沼栗原等の宿々に寄って"(五人小僧噂の白浪) |
下栗原大宮五所大神 |
 |
2019 |
| 善光寺 |
ぜんこうじ |
血脈(講明治大正7:07) 1件1題 (東京1件) |
甲府市善光寺町 |
甲斐善光寺.「お血脈」のマクラでの説明.武田信玄が信濃から秘仏を移したという.こちらの善光寺にも戒壇巡りがある.最寄りは身延線善光寺駅.
"甲斐国、ここへ善光寺を立てて歿くなりました"(血脈) |
甲斐善光寺 |
 |
2008 |
| 甲府 |
こうふ |
甲府い(弘文柳枝:24) など 30件14題 (圓朝3件, 東京27件) |
甲府市 |
城下町だが,かふふと綴ると情けない.と書いたら甲府駅構内に旧煉瓦倉庫や,"かふふ来の鐘"が展示されるようになった.落語の決めゼリフは,"かふふぃおまゐりぐわんほどき".
"わたくしは、東京の者ではございません。山梨県甲府の者でございますン"(甲府い) |
かふふ驛構内図 |
 |
2008 |
| 甲府城 |
こうふじょう |
西海屋騒動(三芳屋 (1902)) |
甲府市 |
武田氏の居城.別名舞鶴城.関ヶ原の戦い以後は,徳川家の支配するところとなる.天守台に建つひときわ目立つ尖塔は,謝恩碑と呼ばれるもの.大水害後の明治天皇の土地下賜に感謝する意図で,1922(大正11)年に設置された.
"我藩には甲府の城を守護の任とて"(西海屋騒動) |
甲府城 |
 |
2019 |
| 甲府:八日町 |
ようかまち |
五人小僧噂の白浪(大川屋 (1892)) |
甲府市甲府中央2・3 |
甲府が出てくる落語は,「甲府い」くらいしかない.しかし,人情噺となると,「雲霧五人男」「善悪草園生咲分」「五人小僧噂の白浪」「骸骨於松」「片思恋嫉刃」など,多岐にわたる.八日町は,甲州街道が甲府に入る街路.甲州印伝は,鹿革に漆で模様をつける技法.財布や巾着などの小物から,バッグまで幅広い品揃え.旧八日町にある印傳屋の二階に博物館が開かれている.
"柳町の角まで遣って来るト八日町の方から来たります男"(五人小僧噂の白浪) |
印傳博物館記念印 |
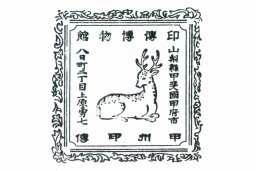 |
2019 |
| 甲府:肴町 |
さかなまち |
五人小僧噂の白浪(大川屋 (1892)) |
甲府市中央あたり |
魚町(うおまち).魚を扱う店が並んでいたことに由来.城の東の南北路に沿って4ヶ所に分かれている.甲州名物アワビの煮貝を扱うみな与は創業400年の老舗.
"肴町と申す処へ剣術の道場を出し"(五人小僧噂の白浪) |
煮貝屋みな与 |
 |
2019 |
| 甲府:柳町 |
やなぎまち |
骸骨於松(毎日新聞 (1897))など |
甲府市中央あたり |
八日町の西にあたり,桜町の東の南北路.節分の大神宮祭は,甲府の春を祝う賑やかなお祭り.厄払いの縁起物を扱う露店がたち並ぶ.
"甲府の柳町とか云ふ所で、相応な呉服屋だとサ"(骸骨於松) |
柳町大神宮 |
 |
2019 |
| 甲府:桜町 |
さくらちょう |
鍋蓋(講明治大正5:22) 1件1題 (東京1件) |
甲府市丸の内1,中央2,4 |
中央2〜4にかけての南北路.今も桜町の名を残している.繁華街で寄席や芝居があった.用例の「鍋蓋」は,「昆布巻芝居」のこと.宮本武蔵が登場する珍しい芝居噺.
"山梨県のエー……甲府桜町の稲積亭と申す席亭へ頼まれまして……よんどころなく興行にまいりました"(鍋蓋) |
桜町商店街 |
 |
2008 |
| 甲府:春日町 |
かすがまち |
片思恋嫉刃(ことばの花, 14 (1892)) |
甲府市中央1 |
駅の南の繁華街.春日あべにゅうと呼ばれる通りと,1本東の裏春日は,甲州随一の歓楽街.写真を撮っていると,朝帰りとおぼしき数人組とすれ違った.
"諸方を廻りまして甲府へ参りました、春日町に相沢屋治兵衛と申しまする旅宿屋(やどや)がございます"(片思恋嫉刃) |
春日通り |
 |
2019 |
| 甲府:酒井町 |
さかいちょう |
善悪草園生咲分(牧野惣次郎 (1885)) |
甲府市中央2あたり |
境町(さかいまち)のこと.甲府城の東,南は竪近習町.甲府市外を歩いていると,通りの名を古地図上に示した案内板がときおり目につく.境町は,甲府城築城にともなう城下町の形成時に成立したとある.
"金は酒井町の田宮の方から仕送りで"(善悪草園生咲分) |
境町通り表示 |
 |
2019 |
| 甲府:新柳町 |
しんやなぎちょう |
五人小僧噂の白浪(大川屋 (1892)) |
甲府市武田3あたり |
甲府には,柳町,元柳町,新柳町がある.新柳町は駅の北.狭い町内で,自治会の掲示板が見つかった程度.速記にある不動堂は見あたらなかった.
"新柳町へ不動堂建立のお話から遂に一条の災ひに逢ひます"(五人小僧噂の白浪) |
新柳自治会掲示板 |
 |
2019 |
| 布施 |
ふせ |
善悪草園生咲分(牧野惣次郎 (1885)) |
中央市布施 |
ここから,甲府市街を離れる.「善悪草園生咲分」では,甲州の博徒が捕り方に追われて富士川に逃げる場面で,甲府から鰍沢へかけての地名がたくさん出てくる.布施の日蓮宗妙泉寺の鬼子母神は,4月に大祭が催される.日に4本ながら,布施から,別の落語地名である南湖へぬけるバスの便がある.
"巨摩郡の布施村の豪農幸左衛門は慈悲といふ事を知らざるうへ"(善悪草園生咲分) |
妙泉寺 |
 |
2019 |
| 我島 |
がしま |
善悪草園生咲分(牧野惣次郎 (1885)) |
中央市成島か |
布施の近くにあるのは,字面の似ている成島(なるしま)または鹿島のことだろう.旧玉穂町の中心部.山梨大医学部からのバスが比較的使いやすい.
"布施村はじめ我島村の農民が打ち連れ立ちて"(善悪草園生咲分) |
成島交差点 |
 |
2019 |
| 町田 |
まちだ |
善悪草園生咲分(牧野惣次郎 (1885)) |
中央市町之田 |
町之田(まちのだ)のこと.成島の南にあたる.このあたりコミュニティバスの便もあるが,都市間交通のために設けられたものではないため,6キロほど歩くしかなかった.
"町田、大和田、今福より東南湖に出で鰍沢に来たり"(善悪草園生咲分) |
町之田案内 |
 |
2019 |
| 大和田 |
おおわだ |
善悪草園生咲分(牧野惣次郎 (1885)) |
中央市大田和 |
大田和(おおたわ)が正しい.町之田の西,さらに西は今福になる.笛吹川をはさんで南北に大田和集落が位置する.身延線の新大田和踏切を通ったが,見える範囲に大田和踏切はなかった.
"町田、大和田、今福より東南湖に出で鰍沢に来たり"(善悪草園生咲分) |
新大田和踏切 |
 |
2019 |
| 今福 |
いまふく |
善悪草園生咲分(牧野惣次郎 (1885)) |
中央市今福 |
旧田富町.釜無川と笛吹川が合流するところに位置する.今福村の中で当たりをつけて訪問したところ,妙法寺に鬼子母神堂板奉納額があがっていた.鬼子母神は1月8日に大祭が催される.
"巨摩郡の今福村で毎年の通りある鬼子母神の祭"(善悪草園生咲分) |
妙法寺鬼子母神堂 |
 |
2019 |
| 上野村 |
うえのむら |
善悪草園生咲分(牧野惣次郎 (1885)) |
西八代郡市川三郷町上野 |
旧三珠町の中心部.上野は,市川團十郎発祥の地とされている.甲斐上野駅の南,丘の上の歌舞伎文化公園に,三升をかたどった市川團十郎発祥之地碑がある.初代團十郎の祖父の堀越十郎が,武田氏に仕えたという.十代目海老蔵(11代團十郎)の撰文で,1984年に建碑された.速記にある寺も実在する.高野山真言宗河浦山薬王寺.甲斐百八霊場第95番札所.
"八代郡上野村なる薬王寺において"(善悪草園生咲分) |
市川團十郎発祥之地碑 |
 |
2019 |
| 市川:陣屋 |
じんや |
善悪草園生咲分(牧野惣次郎 (1885)) |
西八代郡市川三郷町市川大門171 |
市川大門の中心部は,市川本町駅の北になる.街道にあたる中央通りの南に市川陣屋があった.明和2(1765)年に代官出張所が置かれ,寛政7(1795)年に正式に陣屋となった.明治に入って陣屋建物は,郡役所や役場として使われた.現在は,正門のみが裏道に移築されて現存する.
"八代郡市川の陣屋へ訴へ出でたによって"(善悪草園生咲分) |
市川陣屋正門 |
 |
2019 |
| 東南湖 |
ひがしなんこ |
善悪草園生咲分(牧野惣次郎 (1885)) |
南アルプス市東南湖 |
東南湖(ひがしなんご).今福から釜無川を渡ったところ.写真の八幡社は,文禄3(1594)年の銘を持つ銅製神鈴を所蔵する.東南湖には,奈胡庄を支配した奈胡十郎義行の墓もある.
"町田、大和田、今福より東南湖に出で鰍沢に来たり"(善悪草園生咲分) |
東南湖公会堂交差点 |
 |
2019 |
| 茨沢 |
ばらざわ |
雲霧五人男(金桜堂 (1886)) |
南アルプス市荊沢 |
荊沢(ばらざわ).富士川街道に面する.茨沢交差点の北で,道がクランクしている.そこに1891(明治24)年創業の菓子屋があるが,もう営業していなかった.漆喰仕上げの登録有形文化財.
"甲斐国巨摩郡茨沢村に市川文蔵といふ豪農あり"(雲霧五人男) |
荊沢交差点 |
 |
2019 |
| 黒沢 |
くろさわ |
善悪草園生咲分(牧野惣次郎 (1885)) |
西八代郡市川三郷町黒沢 |
鰍沢口駅の西.このあたりの富士川には,北から青柳,黒沢,鰍沢の河岸があった.
"黒沢道へかかりては大塚市川の陣家あり"(善悪草園生咲分) |
黒沢河岸あと |
 |
2019 |
| 昌福寺 |
しょうふくじ |
鰍沢(青圓生08:07) など 4件1題 (東京4件) |
南巨摩郡富士川町青柳町483 |
ここから人情噺を離れ,「鰍沢」の世界に入る.一連の身延巡りの行程で,まずは,青柳の昌福寺.虫切り加持を行う大きな寺.
"青柳の昌福寺へお詣りを致しまして、それから小諸山"(鰍沢) |
昌福寺 |
 |
2014 |
| 法論石 |
ほうろんせき |
鰍沢(青圓生08:07) など 5件1題 (東京5件) |
南巨摩郡富士川町小室707 |
懸腰寺.小室山への途中.土地の法印との間で法論が起きた際,空中に石を留めた地.法論石は地面から床板を越えて堂内に顔を出している.床下の柱には,「鰍沢」を得意とした四代目圓生の署名の墨あとが残っている.
"法論石を出ましたのが、今の時間でいう午後二時頃でございましょうか"(鰍沢) |
法論石 |
 |
2014 |
| 小室山 |
こむろさん |
鰍沢(騒人名作06:14) など 13件2題 (圓朝3件, 東京10件) |
南巨摩郡富士川町小室3063 |
妙法寺.犬が身代わりになって食べた饅頭の毒を護符で消した日蓮聖跡.この毒消し護符は薬事法にひっかからないが,同じく歴史ある赤膏はダメとのこと.丑の刻詣りが合法なのと裏返し.ここの護符をもらっておいたおかげで,月の輪お熊に盛られた玉子酒の毒が消え,体がうごくようになった.
"そのうちに心づいたのが、小室山から受けてきた毒消しの御符"(鰍沢) |
妙法寺山門 |
 |
2014 |
| 鰍沢 |
かじかざわ |
鰍沢(講明治大正7:37) など 23件4題 (圓朝2件, 東京21件) |
南巨摩郡富士川町鰍沢 |
旧鰍沢町.富士川水運の拠点.口留番所があった.船に気をつけろばかりで,身延参りに船旅の場面は出てこない.
"あの鰍沢の舟というものは『乗るも馬鹿、乗らぬも馬鹿』という譬がある"(鰍沢) |
鰍沢口留番所跡 |
 |
1998 |
| 釜ヶ淵 |
かまがふち |
鰍沢雪の酒宴(講明治大正1:05) など 5件1題 (圓朝1件, 東京4件) |
南巨摩郡富士川町 |
鉄砲に狙われた「鰍沢」の旅人が飛び込んだ富士川の急流.
"東海道名代の岩淵へ落とす水勢矢を射るごとく鰍沢の釜ヶ淵というところで、ドウドッと押し流しています"(鰍沢雪の酒宴) |
|
|
|
| 蟹谷淵 |
かにやぶち |
鰍沢(青圓生08:07) など 2件1題 (東京2件) |
南巨摩郡富士川町 |
圓生全集の新装合本では,考証の結果,釜ヶ淵から蟹谷淵に改められた.蟹谷橋というバス停は現存する.
"ずわァッ……という急流、切ッ削いだような崖……ところも名代の釜が淵"(鰍沢) |
蟹谷橋バス停 |
 |
1998 |
| 切石 |
きりいし |
笠と赤い風車(毎日三百年3:14) 1件1題 (東京1件) |
南巨摩郡身延町切石 |
切石,八日市,下山は新作の道中付け.富士川往還の両側に細く集落が続く.
"身延道を鰍沢、切石、八日市、下山と行く方法と"(笠と赤い風車) |
切石 |
 |
2001 |
| 八日市 |
ようかいち |
笠と赤い風車(毎日三百年3:14) 1件1題 (東京1件) |
南巨摩郡身延町八日市場 |
切石のすぐ南の集落.域内に真言宗大聖寺がある.
"身延道を鰍沢、切石、八日市、下山と行く方法と"(笠と赤い風車) |
八日市 |
 |
2001 |
| 伊沼 |
いぬま |
鰍澤(弘文志ん生2:16) 1件1題 (東京1件) |
南巨摩郡身延町伊沼 |
「鰍沢」では道に迷った旅人が犬目を尋ねる例が多い.犬目は確かに鰍沢からすると見当違いだが,伊沼に改めるのもこしらえすぎ.写真の上伊沼は遥か高台にある.
"伊沼へ出て宿をとろうと思ったのが、どうも、雪のために、道に迷っちまいまして"(鰍澤) |
上伊沼を望む |
 |
2001 |
| 屏風岩 |
びょうぶいわ |
善悪草園生咲分(牧野惣次郎 (1885)) |
南巨摩郡中富町宮木 |
富士川左岸にある三角形の崖.早川と富士川の合流点にあり,土砂がたまりやすく,舟運の難所として恐れられていた.写真では木々に覆われているが,かつては屏風を立てたように岩肌がひだとなってそびえており,景勝地としても知られていた.七尋岩も似たようなものだろうが,未詳.
"人の話にも聞いた屏風岩だの七尋岩のと"(善悪草園生咲分) |
屏風岩 |
 |
2022 |
| 下山 |
しもやま |
笠と赤い風車(毎日三百年3:14) 1件1題 (東京1件) |
南巨摩郡身延町下山 |
鰍沢からここで船を下り,身延へ参拝する.本国寺正面に日蓮ゆかりのオハツキイチョウがある.
"身延道を鰍沢、切石、八日市、下山と行く方法と"(笠と赤い風車) |
本国寺 |
 |
2001 |
| 身延山 |
みのぶさん |
鰍沢雪の酒宴(講明治大正1:05) など 51件16題 (圓朝6件, 東京43件, 上方2件) |
南巨摩郡身延町 |
日蓮宗総本山身延山久遠寺.身延の案内は,圓朝の「火中の蓮華」に詳しい.巨大な三門は1907年の再建になる.「鰍沢」に「甲府い」「法華長屋」で身延山が登場する.
"江戸にも居られねエからと言うので一層罪滅ぼしのために身延へ参詣をしようテエので"(鰍沢雪の酒宴) |
身延山久遠寺三門 |
 |
2001 |
| 身延山:五重塔 |
ごじゅうのとう |
め組の喧嘩(にっかつ談志:3) 1件1題 (東京1件) |
南巨摩郡身延町 |
御真骨堂内の五重の塔ではなく身延山頂への道にあったもの.再建の動きがあるらしい.
"甲州身延山で五重の塔が建て替えになり足場を掛けに参ります"(め組の喧嘩) |
|
|
|
| 七面山 |
しちめんざん |
転宅(立名人5:) など 7件4題 (圓朝1件, 東京6件) |
南巨摩郡身延町,早川町 |
標高1989m.山頂付近に敬慎院があり,身延山を守護する七面大明神を祀っている.この敬慎院に参籠し,富士の向こうに昇る日の出を拝むのが習わし.かつては七面山は女人禁制だった.家康側室のお万の方が参道入口の白糸の滝を浴び,神力坊に参籠したところ,七面大明神が現れたという.そこから敬慎院までの50町の参拝路が続いており,途中には4ヶ所の坊と,町ごとの燈籠が参詣の励みになる.「甲府い」でも,女の身では七面山へは登れまいと言われる.写真のコブのようになったところが,七面山山頂になる.
"甲州の身延へ回って、七面山のお砂がいただきたいね"(転宅) |
七面山敬慎院 |
 |
2022 |
| 南部 |
なんぶ |
笠と赤い風車(毎日三百年3:14) など 2件2題 (圓朝1件, 東京1件) |
南巨摩郡南部町 |
富士川の通運の中心地.東北南部氏のルーツ.火祭りは盆の行事.河川敷で燈籠流しや玉入れのような投げ松明,百八たいが行われ,臨時列車も出る.
"北へ上って万沢、南部、身延と十三里行くのとがございました"(笠と赤い風車) |
南部の火祭り看板 |
 |
2009 |
| 万沢 |
よろずさわ |
笠と赤い風車(毎日三百年3:14) など 2件2題 (圓朝1件, 東京1件) |
南巨摩郡南部町万沢 |
万沢(まんざわ).甲駿境の口留番所があった.
"北へ上って万沢、南部、身延と十三里行くのとがございました"(笠と赤い風車) |
万沢口留番所跡 |
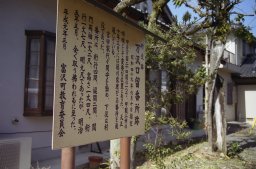 |
2001 |
| 北口 |
きたぐち |
富士詣り(騒人名作06:17) など 2件1題 (東京2件) |
富士吉田市 |
ここからは「富士詣り」になる.富士登山の北口,富士吉田口を指す.こちら側が本来の登山路で,「富士詣り」でも北口から登る.
"昔江戸の道者は皆甲州へ行って、北口から登山いたしましたが"(富士詣り) |
北口浅間神社富士登山道入口 |
 |
2000 |
| 一の鳥居 |
いちのとりい |
富士詣り(騒人名作06:17) など 2件1題 (東京2件) |
富士吉田市 |
北口登山路.金鳥居がかつて一の鳥居.昔はじゃまな建物もなく,きれいに見通せたのだろう.
"ここは何てえ所だえ。一の鳥居という所だが"(富士詣り) |
金鳥居 |
 |
2000 |
| 馬返 |
うまがえし |
富士詣り(騒人名作06:17) など 2件1題 (東京2件) |
富士吉田市 |
北口登山路.中の茶屋までは5月の連休だけバスが出ていたが,利用者は私だけだった.バスの終点から馬返までは遠い遠い.
"俗に馬返しといって、ここでみんな馬を返すんだ"(富士詣り) |
馬返 |
 |
2001 |
| 五合目 |
ごごうめ |
富士参り(講明治大正6:18) など 7件1題 (東京7件) |
富士吉田市 |
「富士詣り」では吉田口から丁度五合目まで登ったところで,山酔いしておしまい.連休のバスを使って馬返から五合目まで登って日帰りするのは,残雪も深くギリギリの行程だった.
"お前は山に酔ッたな。ヘエ、ここが五合目でございます"(富士参り) |
吉田口五合目 藤森稲荷 |
 |
2001 |
| 北山 |
きたやま |
煮売屋(新和上方復刻:14) 1件1題 (上方1件) |
山梨県か |
腹が減ったのではなく,富士の北という.不明.
"富士山の近くに北山と言うのがある、「どやな腹も北山しぐれ」てな事を言う"(煮売屋) |
|
|
|
| 上九一色 |
かみくいしき |
「面接試験」(落語のごらく 1, 私刊 (2005)) |
甲府市,南都留郡富士河口湖町 |
旧西八代郡上九一色村.書き落語の新作のみ.一つの村が2つに分かれて別々の自治体と合併した珍しいケース.毒ガスサリンを製造して無差別殺人を行ったオウム真理教の本拠地があった.本栖湖の富士は千円札の図柄.
"人並みに驕れる者は久しからず、カミクイッシキ、オームなく"(「面接試験」) |
本栖湖 |
 |
2010 |
| 荒井 |
あらい |
妲妃のお百(にっかつ談志:1) 1件1題 (東京1件) |
山梨県か |
不明.妲妃のお百の出身地.
"甲斐国巨摩郡荒井無宿の彦五郎という金箔附の大泥棒"(妲妃のお百) |
|
|
|
 山梨県
山梨県 

 圓朝地名図譜
圓朝地名図譜