| �n�_�� |
�o�T�Ɠo��� |
�ʁ@�u |
���@�l |
�ʐ^�ƎB�e�N |
| ��J�� |
�����₪�� |
��� |
�����s |
��J��ܖ������Ί݂ɂ́C�O�@��t���M�𓊂��Ċ�ɏ����������̞���������D
"��������J��ɗ�����"�i��쉺�쓹�̋L�j |
�ܖ����� |
 |
2017 |
| �R���̎� |
��܂����̂���� |
��� |
�����s�㔫�Β��`�R�� |
�_���D������l����J���n��ہC�_���剤���ւɐ��₵�ċ��Ƃ������Ƃɂ��D�L���n���\�D
"��h��̋�����A���i������j�ƂĐ̏��R��ЎQ�̎��n��ꂵ���Ȃ�"�i��쉺�쓹�̋L�j |
�_�� |
 |
2017 |
| ������ |
���������� |
��� |
�����s |
��J�쒆�C�_���̏��ɂ��������C1902�i����35�j�N�̍^���Ŗ��v�����D�Ȍ�̍��ڂł�����35�N�̍^���Ń_���ɂȂ����n�_���悭�o�Ă���D
"�J�R ������l �����čs���Ȃ��ꂵ�́A�����i�����������j�Ɖ]��"�i��쉺�쓹�̋L�j |
�@ |
�@ |
�@ |
| ���莛 |
�܂� |
��� |
�����s |
��g�łł́C���������|�܂ł̋L�q��������Ă���D���������Ɏ��@��109���������Ė��莛�ꎛ�ƂȂ�D���̌�C�Ăї։����̎R���ƂȂ�D
"�R���̎���n��ē��̕��ɓo��A���莛�̋����Ȃ�"�i��쉺�쓹�̋L�j |
�@ |
�@ |
�@ |
| ���֓� |
�������Ƃ� |
���, ��� �S1��1�� |
�����s�R�� |
����橖�i�������Ƃ��j�D������������Ў��������n�܂�D�_�������ɂ��C�����̖K�ꂽ�N�ɏ��O�ӂ���ڐ݂��ꂽ�D
"���֓� ���T���O��]"�i��쉺�쓹�̋L�j |
�։�������橖 |
 |
2024 |
| �O���� |
����Ԃǂ� |
��� |
�����s�R�� |
�։����{���D�����̂悤��3�̂̋���ȕ������J����D�q�ϗL���D
"�O�����͓��i�������ˁj����h��̑剾���ɂ�"�i��쉺�쓹�̋L�j |
�։����O���� |
 |
2024 |
| �{������ɔn�� |
�ق�݂��Ƃ� |
��� |
�����s�R�� |
�Â��G�t���̕����D�։����O�������D�����O�������̖{�n���ł�����ω��C����ɔ@���C�n���ω������ԁD
"�{������ɔn���ɂ��āA ���T���ڗ]"�i��쉺�쓹�̋L�j |
�O�������i�G�t���j |
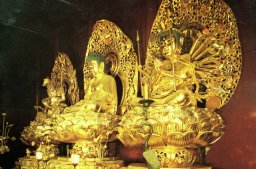 |
�@ |
| ��e�̑咹�� |
�݂��������̂����Ƃ肢 |
��� |
�����s�R�� |
�����ˎ单�c�����̊�i�D������O�̐Βi�͐�l�e�`�ƌ����C���ߖ@�����čL��������v�ɂȂ��Ă���D
"��e�̑咹���� ���a�l�N ���c�}�O�� ����苐�� ���Ȃđ���グ����"�i��쉺�쓹�̋L�j |
���Ƌ{��m���� |
 |
2025 |
| �d�� |
�����イ�̂Ƃ� |
��� |
�����s�R�� |
�����̐����D���l�ˎ���䒉���̊�i�i��ɏĎ��j�D
"���d������ �O�\�O�ԗ] �����B����"�i��쉺�쓹�̋L�j |
�d�� |
 |
2000 |
| �\��x���蕨 |
���イ�ɂ��ق���� |
��� |
�����s�R�� |
�\��x�̒����́C�d���̈�ԉ��̊K�ɂ���D���p�ɍ��킹�������Ȃ̂ŁC���ʂɌ�����E�T�M�͓��ʂ��Ă���D
"����O������ߏ\��x����"�i��쉺�쓹�̋L�j |
�d���K���� |
 |
2024 |
| �ԏ� |
�� |
��� |
�����s�R�� |
�����R���ɂ͂������ԏ�������C�Q�q�҂ɖڂ����点���D���ł����ԏ��͍���D�\�ԏ��́C���͂��D�Ȃǂ̃O�b�Y�̔��D
"�E�͔ԏ��̍��E�ɐΊ_�̓��ɑ����"�i��쉺�쓹�̋L�j |
�\�ԏ� |
 |
2024 |
| �A������ |
����߂��� |
��� |
�����s�R�� |
�\�剺�̐����Ί_���̋��D�����̈��[�ې̕����T�C�Y�͑傫���D
"���G �O�ԗ] ���ɃA�����Ƃ���"�i��쉺�쓹�̋L�j |
�A������ |
 |
2000 |
| ���ʎO������ |
���傤�߂�݂ނ˂Â��� |
��� |
�����s�R�� |
���Ƌ{�̎Q�q�����D���ʍ��E�ɂ͐m�����D�����̐_�������ňꎞ�ڂ��ꂽ�D
"���ʎO���i�ނˁj����������q�̒���"�i��쉺�쓹�̋L�j |
�\�� |
 |
2024 |
| �������q�̒��蕨 |
���炵���̂ق���� |
��� |
�����s�R�� |
�ȉ��C�\��̒����̐����D���O�ɓ����q�D
"�������q�̒����A�e���Ē���ۓ����@�_�ɕ^"�i��쉺�쓹�̋L�j |
�\�� �����q |
 |
2024 |
| �e���Ē��� |
�����̂����ڂ� |
��� |
�����s�R�� |
�\��̒����D���F�����Ă��Ă����D
"�������q�̒����A�e���Ē���ۓ����@�_�ɕ^"�i��쉺�쓹�̋L�j |
�\�� �e�̒��� |
 |
2024 |
| �ۓ����@ |
��������傤�� |
��� |
�����s�R�� |
�\������l��������ۂ̒����̂��Ƃ��낤�D
"�������q�̒����A�e���Ē���ۓ����@�i��������傤�сj�_�ɕ^"�i��쉺�쓹�̋L�j |
�\�� �ۂ̒��� |
 |
2024 |
| �_�ɕ^ |
�����ɂЂ傤 |
��� |
�����s�R�� |
�\��̒����D�_�ɏ���Ă���̂��сD���_���̌Ղ��^�ƌĂ�Ă����D
"�_�ɕ^�A��������Ɍ܍�"�i��쉺�쓹�̋L�j |
�т̒��� |
 |
2024 |
| ���̓��� |
�����̂Ƃ��낤 |
��� |
�����s�R�� |
�\�傩�璆�ɓ������Ƃ���D���̓��ĂƐΓ��Ă�����ł���D������ʂɕ~���Ă���I�́C�N�P��{�����e�B�A���Ђ�����Ԃ��đ|������D
"���̓��Ă͋�����̌��[�A���ւ��ʒ��Ȃ�"�i��쉺�쓹�̋L�j |
���Ƌ{�̓��� |
 |
2024 |
| �O�_�� |
���� |
��� |
�����s�R�� |
��C���C���R���̍Z�q����̕ɁD�Ց����Ȃǂ��ۊǂ���Ă���D
"�O�_�ɂ���A�O���i�݂ނˁj��h��A�����͓t��"�i��쉺�쓹�̋L�j |
��_�� |
 |
1990 |
| ��ۂ̒��蕨 |
���������̂ق���� |
��� |
�����s�R�� |
��_�ɂ̑��ʂɂ��锒����̏ہD���T�H�̉��G�Ƃ����D
"��m�_�ɁA������j�����ɑl�F�Ɣ��F�̑�ۂ̒�������"�i��쉺�쓹�̋L�j |
��_�ɒ����̏� |
 |
2024 |
| ��X |
�����܂� |
��� |
�����s�R�� |
���Ƌ{���̗B��̔��ؑ���̌����D�ȑO�̖K��ł́C���J���ȕ��͋C�̔��n�����ۂɎ����Ă����D
"��X�f�i���炫�j�̉��̒���"�i��쉺�쓹�̋L�j |
�_�X�� |
 |
2024 |
| ���̒��蕨 |
����̂ق���� |
��� |
�����s�R�� |
�_�X�ɂ̒�����8�g�̉��̒��蕨������D8����ʂ��ĉ��̈ꐶ��`���Ă���D�����長�����錾�킴��̎O���͂��̈�D�C������āC���g�̂������ɂȂ����ƕ]���D
"��X�f�i���炫�j�̉��̒���"�i��쉺�쓹�̋L�j |
�O�� |
 |
2024 |
| ���� |
�݂��� |
��� |
�����s�R�� |
�����̒��͉ԛ���D�瓇�˂̊�i�ŁC�����Ő����D�E�͉ƌ���i�̓��������D
"�����͐Β��i�������イ�j�Q�ɗ��̒���"�i��쉺�쓹�̋L�j |
�䐅�� |
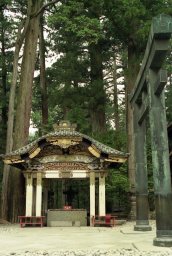 |
1990 |
| �g�ɗ��̒��� |
�Ȃ݂ɂ�イ�̂ق� |
��� |
�����s�R�� |
�����̒����D���ʍ��E�Ɉ�̗��������Ă���D���̗��ɂ͗��������Ă��Ĕg����Ĕ��Ă���D
"�Q�ɗ��̒���A�ɋ�����ł�����A�瓈���̊�i�Ȃ�"�i��쉺�쓹�̋L�j |
�����̗��̒��� |
 |
2024 |
| ��ؓS�̓��� |
�Ȃ��Ă̂Ƃ��낤 |
��� |
�����s�R�� |
���ɒB���@�̊�i�D�ɒB�Ƃ̋�j�䂪�����Ă���D�A���S�ނ𗘗p���C�����������Ƃ����D
"��ؓS�̓��Ă͐������i"�i��쉺�쓹�̋L�j |
��ؓS���� |
 |
1990 |
| �����O |
���イ����낤 |
��� |
�����s�R�� |
�z����̍��E�ɏ��O�ƌۘO�����ԁD���O�͌������ĉE���D�ۘO�Ɠ����悤�Ɍ����邪�ו��̒����͈قȂ�D
"�����O�ۘO����"�i��쉺�쓹�̋L�j |
���O |
 |
1990 |
| �ۘO |
���낤 |
��� |
�����s�R�� |
������͍����D�ۘO�̕����������n�ゾ�Ƃ����D
"�����O�ۘO����"�i��쉺�쓹�̋L�j |
�ۘO |
 |
1990 |
| �@���� |
�͂��ǂ��낤 |
��� |
�����s�R�� |
�͂�̂悤�ȃf�U�C���̘@���ẮC�I�����_����̊D
"�@���Ă͎O�\�����i�T�_�j�̐C�䂠��A��������Ȃ�"�i��쉺�쓹�̋L�j |
�@���� |
 |
2024 |
| ���H�� |
�ނ��������� |
��� |
�����s�R�� |
���N�ʐM�g�̊D�����Ɍ����Ă��邱�Ƃ��璎�H���̕ʖ�������D
"���N��茣��̒ޏ����ꖼ������Ƃ���"�i��쉺�쓹�̋L�j |
���N�� |
 |
2024 |
| �ނ蓕�� |
��ǂ��낤 |
��� |
�����s�R�� |
�����ɔ[�߂��Ă���̂Ō��Â炢�D�������疠��̘r�����{����ɍ����o����Ă���`�D�������C�ȑO�͌����l����]�ł����͂��D
"�������ɂ�茣���� �O�\�� �ޓ��Ă���"�i��쉺�쓹�̋L�j |
�ޓ��� |
 |
2024 |
| ���{�� |
���イ�ق�ǂ� |
��� |
�����s�R�� |
���Ƌ{�{�n���̖�t�@�����J��D���w�V��ɖ����`����Ă���D1961�N�ɏĎ��������Č�����Ă���D
"���̕��� ���{������B��h����E�����̒�"�i��쉺�쓹�̋L�j |
�{�n�� |
 |
2024 |
| �V��̗� |
�Ă傤�̂�イ |
��� |
�����s�R�� |
�L���Ȗ��D�Č��D������l�C�ŁC���q���s�[���Ɩ炵�āC�������间�̖��������Ă����D�ʐ^�͊G�t���̕����D
"�V��̗��͈��M�i�₷�̂ԁj�̕M�Ȃ�"�i��쉺�쓹�̋L�j |
���i�G�t���j |
 |
�@ |
| �z���� |
�悤�߂����� |
���, ��� (�� ����11��) �S12��8�� |
�����s�R�� |
�������Ƌ{�̏ے��C�z����D�ȉ��C���̒����ނ��ׂ����������Ă���D
"��������\���\�ƌv��Ȃ�Ǒ��̒��ɂ��������ꂽ��͗z����"�i��쉺�쓹�̋L�j |
�z���� |
 |
2024 |
| ��d���؋����� |
�ɂ��イ���邫����͂���イ |
��� |
�����s�R�� |
�z���剮�����D���̉��C��i�ɏd�Ȃ��������̂����C���i�ɒ���ꂽ���@�̕��́C���ł͂Ȃ����Ƃ�����b���Ƃ����D
"�l�����j���ɓ��i�������ˁj����d���؋��������̊Ԗ���"�i��쉺�쓹�̋L�j |
�z���� �������� |
 |
2024 |
| �� |
�͂��� |
��� |
�����s�R�� |
�E����Q�{�ڂ��O���䂪�t���ɒ����Ă���t���D�ȑO�͎�C�ꂵ�Ă������C�^�����ɏC������Ă���D
"���͒̊ۂɂĈ��H�̖�"�i��쉺�쓹�̋L�j |
�z����̒� |
 |
2024 |
| �z |
���� |
��� |
�����s�R�� |
�z���吳�ʂɌf����ꂽ�z�D���Ƒ匠���Ƃ���D�㐅���V�c�̛��M�D
"�z�͌㐅���@�̌䛂�M�Ȃ�"�i��쉺�쓹�̋L�j |
�z���� �G�z |
 |
2024 |
| �����q�̊ے��� |
���炶���̂܂�ڂ� |
��� |
�����s�R�� |
�������q�┒�F�ȂǑ����̓����q���z����Ɍ�����D
"�����̊Ԃ͓����q�̊ے���"�i��쉺�쓹�̋L�j |
�z���� �����q |
 |
2024 |
| ���� |
���イ���� |
��� |
�����s�R�� |
�������i�D�z���吳�ʌ���7�̂̒����̒����ɂȂ�D�����̉E��ɂ͑i��������o���i�l�������Ă���D�����́C����Ȃ�����i�l�̘b�Ɏ����X���Ă���D
"��ʂ�͐l�����b�̒���A���̐l���� ���� ���"�i��쉺�쓹�̋L�j |
�z���� �������i |
 |
2024 |
| �E�q |
������ |
��� |
�����s�R�� |
�E�q�ώD���ʂV�̂̒����̍�����3�ԖڂɂȂ�D�̗͂���̂悤�ɂƁC���̗�����v���D���ʂ̎c��́C�e�ՁE�͌�ȂnjN�q�l�|�������Ă���D
"���� ��� �E�q ���� �O��"�i��쉺�쓹�̋L�j |
�z���� �E�q�ω� |
 |
2024 |
| �O�� |
���傤 |
��� |
�����s�R�� |
�Ռk�O�D������4�̂̒����̉E����2�ԖځD�d���E�������E���C�Â�3�l�D�Ռk���܂��Ɛ������d���@�t���C2�l�Ƃ̘b�ɖ����ɂȂ��Ďv�킸����n���Ă��܂���������Ƃ������D�����̋L����"�Z�� �l�F ��N"�͕s���D���̒����́C�|�z�O����C���́u�S���v�Ȃǂ̐�l�������Ă���D
"���� �O�� �Z�� �l�F ��N ���Ȃ�Ɖ]��"�i��쉺�쓹�̋L�j |
�z���� �Ռk�O�� |
 |
2024 |
| �����ɂ݂̗� |
�͂��ۂ��ɂ�݂̂�イ |
��� |
�����s�R�� |
���T�H�̉��G�ɂ��D�̂�����_�͏��藴�D���������D�����܂ł��z����̐����ɂȂ�D
"�V��͌Ö@�ጳ�M�����ɂ݂̗�"�i��쉺�쓹�̋L�j |
�z���� �~���� |
 |
2024 |
| ����L |
�˂ނ�˂� |
����(�O���u��) �Ȃ� (�� ����17��, ���2��) �S20��12�� |
�����s�R�� |
���Ђ̓����D���r�ܘY�̍�ŁC���Ƌ{�ň�ԗL���Ȓ����D�L�̗����ɂ͐��������Ă���C�L������߂�̂�Y���قǎ��܂鐢�Ƃ������Ƃ�\���Ă���D�K�C�h���@���Đ�������̂������͂�����낾�����D
"�{�Ђ̌��̎R��ɓ����ɖ������r�ܘY������̖���L�̒����̏�ɖڂ���������"�i��쉺�쓹�̋L�j |
����L |
 |
2024 |
| �S��� |
������ |
��� |
�����s�R�� |
�{���œS��Ƃ̐���������D�ꏊ�͐Βi���炵���̂ō≺��Ƃ������C����͓S��ł͂Ȃ��D�Βi��ɂ͒����傪����D
"�S����L��Ƃ��ӂ����Ƃ��Ȃ肫"�i��쉺�쓹�̋L�j |
�≺�� |
 |
2024 |
| �Βi |
�������� |
��� |
�����s�R�� |
���Ђ֑����Q���̒����Βi�D
"�v���Βi��o��A�q�a"�i��쉺�쓹�̋L�j |
�ƍN�_�ւ̐Βi |
 |
2024 |
| �q�a |
�͂��ł� |
��� |
�����s�R�� |
���В���D�ƍN�_�̔q�a�D
"�v���Βi��o��A�q�a"�i��쉺�쓹�̋L�j |
�ƍN�_ �q�a |
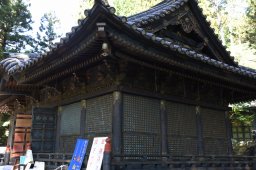 |
2024 |
| �� |
�ق��Ƃ� |
��� (�� ����1��) �S1��1�� |
�����s�R�� |
��Q�@�_�ƈႢ�C�ƍN�_�͏�Ɍ��J���Ă���Ă���D
"����i�������ɓ����͉̕ƍN����⍜�����������Ɖ]��"�i��쉺�쓹�̋L�j |
�ƍN�_ |
 |
2024 |
| ��r�̐_�� |
�ӂ���̂���� |
��� |
�����s�R�� |
������r�R�_�ЁD���Ƌ{�C�։����ƂƂ��ɓ�����Јꎛ�ƌĂ��D�j�̎R�i��r�R�j��_�̂Ƃ���D�j�̎R���ɉ��{�C���T���ΔȂɒ��{�K������D�q�a���艜�̐_���͔q�ϗL���D�ʍ��̉������Ă���C�卑�a�Ȃǂ�����D
"�������r�̐_�Ђ�q���č�������"�i��쉺�쓹�̋L�j |
������r�R�_�� |
 |
2025 |
| ��̓� |
�ӂ��̂ǂ� |
��� |
�����s�R�� |
��r�R�_�А��ʂ̐Βi���~���ƁC�ʐ^��O�̏�s���Ɩ@�ؓ��̓�̂������L���łȂ����Ă���D�]�ˊ��i���ɂ������悤�ȓ��F������C�S�����ƌĂꂽ�D
"�������Č���ɓ�̓�����A�S�q��_�����u���Ƃ���"�i��쉺�쓹�̋L�j |
��� |
 |
2025 |
| ���ᓰ |
������ǂ� |
��� |
�����s�R�� |
�V�C�m���i�����t�j�̗�_�D���݂͗�������Ȃ��D
"���̊Ԃ̍������� ���ᓰ�V�C�m�� �̕_��"�i��쉺�쓹�̋L�j |
���ᓰ |
 |
2000 |
| �V�C�m���̕_�� |
�Ă��������傤�̂т傤���� |
��� |
�����s�R�� |
��s������̎Q�q�H�����łȂ��C���≺����̓��ɂ��C���L�n�̂��ߗ����֎~�ƕ\������Ă����D���Ă͎Q�q���̂͋ւ��Ă��Ȃ��悤�������D
"���̊Ԃ̍������� ���ᓰ�V�C�m�� �̕_��"�i��쉺�쓹�̋L�j |
�V�C�m���� |
 |
1990 |
| ��Q�@�a��쉮 |
�����䂤����ł��܂� |
��� |
�����s�R�� |
��������́C�O�㏫�R�ƌ����̕_����Q�@�i�����䂤����j�̐����ɂȂ�D��쉮�̘L���������܂ŕ������Ƃ������ꑽ���Ƃ̚����̏q��������D
"�O��ƌ��� ��Q�@��쉮 �̎�h��̍���"�i��쉺�쓹�̋L�j |
�@ |
�@ |
�@ |
| ���� |
�݂��� |
��� |
�����s�R�� |
�䐅�ɁD��Q�@�̗������̐�C�m��������������Ƃ���ɂ���D12�{�̒��͌�e�D
"�����̓V��͈��M�̉�i���j"�i��쉺�쓹�̋L�j |
��Q�@ ���� |
 |
2024 |
| �����̓V�� |
�݂���̂Ă傤 |
��� |
�����s�R�� |
�����V��ɂ́C���i�^���M�̖n�G�̗����`�����D���ՂɎp���f��Ƃ����D
"�����̓V��͈��M�̉�i���j"�i��쉺�쓹�̋L�j |
��Q�@ �����̗� |
 |
2024 |
| ��V�� |
�ɂĂ���� |
��� |
�����s�R�� |
�����̍���C�Βi��̘O��D�����L�ڂ̓�V���ɂ݂��������D
"��V��́A�����V�A�L�ړV"�i��쉺�쓹�̋L�j |
��Q�@ ��V�� |
 |
2024 |
| �����̓�_ |
�ӂ��炢�̂ɂ��� |
��� |
�����s�R�� |
��V��̗��ʂ͕��_���_���D�K�C�h�̐����𓐂ݕ�������ƁC�w�̐����]�X�Ɛ���w�I��������Ă����D
"���͕����̓�_"�i��쉺�쓹�̋L�j |
��Q�@ ���_���_ |
  |
2024 |
| ���O�E�ۘO |
����낤���낤 |
��� |
�����s�R�� |
�鍳��Ɏ���Βi���̍��E�ɕ��ԁD
"���o��ď��O�ۘO���ɖ鍳�傠��"�i��쉺�쓹�̋L�j |
��Q�@ ���O�ۘO |
  |
1990 |
| �鍳�� |
�₵����� |
��� |
�����s�R�� |
���떀���E���ɗ��E�G���Ӊ��E犍�ɗ��̎l�鍳���l�����߂Ă��邽�߁C�鍳��̖������Ă���D�{���ʂ�C�鍳��͉��O�̒����ŏ����Ă��邽�߁C���O��Ƃ��Ă��D
"�鍳�傠��B�ʊ_���̑�����������̖����ɂ�"�i��쉺�쓹�̋L�j |
��Q�@ �鍳�� |
 |
2024 |
| �������� |
���ǂ��낤 |
��� |
�����s�R�� |
�Ƃ���ς���āC��r�R�_�Г��̓������Ă̐����D�l�����Ԃ炩�������߁C�a�����ꂽ�������c���Ă���D�q�ϗL���D
"�����Ă͓�r�_�Ђ̑O�ɂ���"�i��쉺�쓹�̋L�j |
�������� |
 |
2024 |
| ���̉@ |
�����̂��� |
��� |
�����s�R�� |
�Ăё�Q�@�ɖ߂�D2000�N�ɏ��̈�ʌ��J���������D���̔q�a�C������C�Ƒ����D
"���̉@�����ɍc�Ö傠��"�i��쉺�쓹�̋L�j |
��Q�@�@�ƌ��_ |
 |
2000 |
| �c�Ö� |
���������� |
��� |
�����s�R�� |
���̉@�̓����D���{���v�킹�����̖�D
"���̉@�����ɍc�Ö傠��"�i��쉺�쓹�̋L�j |
��Q�@�@�c�� |
 |
2024 |
| �䋟�� |
���������� |
��� |
�����s�R�� |
��Q�@�������č����ɂ���D�H�����^��������D�������ƌ��_���J�̎��ɒʘH�ƂȂ������߁C���߂Ėڂɂł����D
"�����䋟��"�i��쉺�쓹�̋L�j |
��Q�@�@�䋟�� |
 |
2000 |
| �����@ |
��イ�������� |
��� |
�����s�R�� |
�����@�D��Q�@�̕ʓ����߂�D���J����Ă��Ȃ��D
"�����@�A����̎�"�i��쉺�쓹�̋L�j |
�����@ |
 |
1990 |
| ����̎� |
�����̂��̂₵�� |
��� |
�����s�R�� |
��Q�@��������Ƌ{������C����ւ̒T���H���ʂ��Ă���D�ȉ��C�e���̌��ǂ�����������Ă���D����_�Ђ́C�T���H�̂����Ƃ����ɂȂ�D�ʐ^�̒����͉^�����̒����ƌĂ��D�z���ɂ����镔���Ɍ��������Ă���C����3������,
3�Ƃ��ʂ�Ɗ肢�����ł����Ȃ��Ƃ����D���́C�̑���ɃX�|���W�{�[�����p�ӂ���Ă���D
"����̎ЁA����"�i��쉺�쓹�̋L�j |
����_�Љ^�����̒��� |
 |
2024 |
| ���� |
�قƂ����� |
��� |
�����s�R�� |
����_�Ђւ̓r���ɂ���D���Ă�3�`4�̂̕����Ɏ������������Ƃ������C����ɂ�莸��ꂽ�D
"����A�q���"�i��쉺�쓹�̋L�j |
���� |
 |
2024 |
| �q��� |
�����˂��� |
��� |
�����s�R�� |
����_�Ѝ���̂ǂ�Â܂�ɂ���D���ʒʂ�C�q�����̗쌱������Ƃ����D
"�q��i�����˂����j�A�f�ˑ�"�i��쉺�쓹�̋L�j |
�q��� |
 |
2024 |
| �f�ˑ� |
�����߂� |
��� |
�����s���� |
�����̑�D����_�Ў�O�C�V���ɉ˂���D�O�@��t���C�Ƃ����Ƃ����D�f�ˑ�͕ʖ��D�ܖ������̓�̑��������Ƃ���ɂ��f�ˑꂪ���邪�C�ꏊ���炢���Ă�����炵���D
"�f�ˑ�A�ѐ���"�i��쉺�쓹�̋L�j |
�f�ˑ� |
 |
2024 |
| �ѐ��� |
�߂����肷�� |
��� |
�����s�R�� |
500�N�ȏ�O�C�m����������Q���ɐ����{�̃X�M��A�������߁C�������ƌĂ��D���ł��ѐ����i�������肷���j�́C�������猩��Ƙq�ɔт����悤�Ɍ����C�ڗ����Ă����D����ɑ��̖ɒǂ�����Ė��v�����D1963�N�̓˕��œ|��Ă��܂����D
"�ѐ����A��|��"�i��쉺�쓹�̋L�j |
������������ |
 |
2024 |
| ��|�� |
�������� |
��� |
�����s�R�� |
�k��_�Ђ��D�Q���e�ɂ���D����̓c�S�P��������|�����Ɠ`����D�ѐ����́C�����Ƒ召�ׂ��̔�Ƃ̒��Ԃ��炢�̓����ɂ������D
"��|�A�O�{������������"�i��쉺�쓹�̋L�j |
��|�� |
 |
2024 |
| �O�{�� |
����ڂ� |
��� |
�����s�R�� |
����_�Ђ̗��D����Ђ̍Ր_���~�肽�Ƃ���Ƃ����D�R�{�̃J���}�c�͏��a�̏I���ɑ������Ō͎������D
"�O�{�����������Ĉē��҂Ɉ�X�����ڂ����ꂽ���"�i��쉺�쓹�̋L�j |
�O�{�� |
 |
1990 |
| �Ԗ��R |
�����Ȃ�� |
��� |
�����s |
��g�ł̃��r�́C�����Ȃ���D�ԓ�R�i�����Ȃ�����j�D�W��2010m�D����R�̓��ɘA�Ȃ�D
"�l�A�ܒ� �s���قǂɐԖ��R��藎���鐅�������܂���"�i��쉺�쓹�̋L�j |
�ԓ�R��]�� |
 |
1990 |
| �ϐ������{�̐Β� |
�����悤�̂����Â� |
��� |
�����s���_�� |
�@�ӗ֊ϐ�����F�ƒ���ꂽ�Γ����낤�D���@�̓����߂��ɂ���D
"���̌��E�� �ϐ����Ɖ]�ӁB���{�̐Β˂�������"�i��쉺�쓹�̋L�j |
���@ �ϐ����Γ� |
 |
2024 |
| �����R�����@ |
�ɂ����������������� |
��� |
�����s���_�� |
��g�ł̋L�q�́C�����R�����@�i���키�������j�D���_���@�i������������j�̂��Ƃ��낤�D���@�����̎��H�̏�D���Ƌ{�߂������C�����͐l�C�����Ȃ��D�{���ʂ�{���͈���ɔ@���C����l�D�ۑm��E�̔�́C��������������m���C�Ƃ̐��Ȃ��Ԃł��邱�Ƃ������D
"���͓����R�����@ �Ƃē��{�̑厛�O������"�i��쉺�쓹�̋L�j |
���@ �R��ۑm��E�� |
 |
2024 |
| ���k�� |
�������� |
��� |
�����s���_�� |
���d�D�s���֎������̕����������Ă���D��������@�̓����߂��ɗ����Ă���D
"��������̕����֎�s�R����Ɛ[����ɂ�������k����"�i��쉺�쓹�̋L�j |
���@ ���d�� |
 |
2024 |
| ���O�� |
����낤�ǂ� |
��� |
�����s���_�� |
��g�ł̃��r�́C���₤�낤�����D�����̑��L��i�ł́C�Â��ǂ݂ł���"����낤"�Ə����Ă���̂ŁC���̃��r���M�p�ł��Ȃ��؋��̈�D���_���@�̗��{����̏��O�D����16�N���Ƃ�����D���͐펞���o���ꂽ�D
"���o��Β���̖T��ɏ��O������"�i��쉺�쓹�̋L�j |
���@ ���O |
 |
2024 |
| ���~�� |
����ӂ�̂��� |
�ɍ���, ���, ��� (�� ����1��) �S3��3�� |
�����s����C���� |
���Ă̑ꌩ�����̂Ƃ���ɒ��ԏ�ƓW�]�{�݂�����D����������e��܂œk���D��͏㉺��i�ɂȂ��Ă���D
"�ē���A�ꖶ�~��ɉ����B���̓���R�̍ד��ɂ��āA���܂��ܔn�̒ʂӂ̂݁A �ꗢ�̊� �l�Ɉ��͂�"�i��쉺�쓹�̋L�j |
���~�� |
 |
1992 |
| �ᒆ�������̔� |
�������イ�����傤���̂� |
��� |
�����s���� |
��g�łł́C"�ᒆ������"�̋L�q�͂Ȃ��D�������Ă͎O�����̌��D���ԏ�̂Ƃ���ɂ���D�ᒆ������(1717�`87)�͔m�Ԃ̑���q�D
"�J�։����Ƃ��鑤�i�������j�ɐᒆ�������̔肠��"�i��쉺�쓹�̋L�j |
�ᒆ��������� |
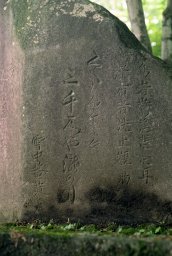 |
1992 |
| ��� |
������ |
��� |
�����s����C���� |
�����̕��ł͖������̈��H�ɕ`����Ă���D�ߔN����������T����悤�Ɍf�����ꂽ���C�~��邱�Ǝ��̂͊ȒP�D
"�̎}�Ɏ�蕍�����������߂Ă₤�₤���ɗ�����"�i��쉺�쓹�̋L�j |
���~��� |
 |
2000 |
| �_�{�䋟�� |
������������ |
��� |
�����s |
��g�ł̃��r�́C���������������D���̓ǂ݂̕�����ʓI���낤�D�������̌䋟���́C���Ƌ{�̔��ؘL����ʂ��Ė{�{�₩��_���̘e�ւƗ��ꂽ�D
"��J��̋��̎�O�ɐ_�{�䋟�� ������̗␅ �����݂�"�i��쉺�쓹�̋L�j |
�{�{���� |
 |
2024 |
| �@�|�o�H�O�| |
| ����� |
������������� |
��� |
�����s���� |
��q�_�ЁD�_�������O�̎�����D���������̉Ύ��ŏĎ����C����ɂ���_�ЎГa�ƒ����C�b���c��D�߂��ɂ͎���̑ꂪ����D
"�O�m�\��N��C��l����Ў���Г��𒆋����Ă�葴�̌�����R�Ɖ��̂�"�i��쉺�쓹�̋L�j |
��q�_�� |
 |
2006 |
| ���R���q�� |
������܂�����ނ� |
��� |
�����s���q |
��g�łɂ͂��̋L�ڂ͂Ȃ��D"������"�ł͂Ȃ�"������"�D���s�s�̓�͂���D��������ˑR�Ɨᕼ�g�X���̐������͂��܂�D�������j���̊�i�ɂȂ�D
"���R���q�� �͓��S ��K�i�������j���R���܂Ŏ�������i�ɐA�����ꂵ��"�i��쉺�쓹�̋L�j |
���q�����؊�i�� |
 |
2025 |
| ��K�� |
�������ނ� |
��� |
�����s��K�� |
��g�łɂ͂��̋L�ڂ͂Ȃ��D���s�̖k�̂͂���D��Ð��X���͂����܂Ő����ŁC��K�ɓ��^�̊�i�肪���D
"���R���q�� �͓��S ��K���R���܂Ŏ�������i�ɐA�����ꂵ��"�i��쉺�쓹�̋L�j |
��K�����؊�i�� |
 |
2025 |
 �V����
�V���� 
 ��쉺�쓹�̋L �{��
��쉺�쓹�̋L �{��
