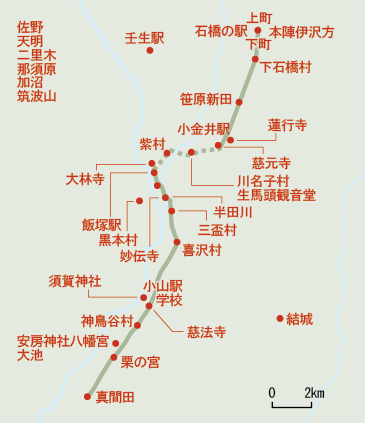| 地点名 |
出典と登場回数 |
位 置 |
備 考 |
写真と撮影年 |
| 栗の宮 |
くりのみや |
上野 |
小山市粟宮 |
岩波版の表記は,粟の宮(あはのみや).粟を栗と誤読したのだろう.写真の西堀酒造は明治4年創業なので,圓朝も目にしたかもしれない.伝統の若盛のほか,純米大吟醸門外不出やウイスキーも生産している.
"七時に出立となり、並木を通り栗の宮出外(ではずれ)に小休み"(上野下野道の記) |
西堀酒造 |
 |
2008 |
| 安房神社八幡宮 |
あわじんじゃはちまんぐう |
上野 |
小山市粟宮1615 |
安房神社.延喜式内神社.かつては地名のように粟宮とも呼ばれた.藤原秀郷が戦勝を祈願したと伝える.
"並木の中場に安房神社八幡宮あり"(上野下野道の記) |
安房神社 |
 |
2008 |
| 大池 |
おおいけ |
上野 |
小山市粟宮1615 |
明治期からは変わっているだろうが,まるで本文にあるような水神の池では真鯉緋鯉が泳いでいた.
"二丁廻りの大池に朱鯉(ひごい)多くゐたり"(上野下野道の記) |
安房神社内水神宮 |
 |
2008 |
| 神鳥谷村 |
しととや |
上野 |
小山市宮本町 |
変わった地名だが,神鳥谷(ひととのや)と読む.小山にも近く,商店や宅地で埋めつくされている.1軒だけ,長屋門づくりのお宅があった.
"是従り神鳥谷村に出で、小山駅に入る"(上野下野道の記) |
日光街道神鳥谷 |
 |
2024 |
| 小山駅 |
おやまえき |
上野 |
小山市 |
藤原秀郷の末裔である小山氏の居城だった.また,家康小山評定の地でもある.小山氏累代の墓は天翁院(本郷町1)にある.
"是従り神鳥谷村に出で、小山駅に入る"(上野下野道の記) |
小山市累代墓 |
 |
2003 |
| 須賀神社 |
すがじんじゃ |
上野 |
小山市宮本町1-2 |
小山近郷の総鎮守.日光街道に東面する.蓬莱鏡,家康の寄進状を所有する.夏の祇園祭が盛大に開かれる.
"左側 須賀神社 駅の中程"(上野下野道の記) |
須賀神社 |
 |
2024 |
| 学校 |
がっこう |
上野 |
小山市宮本町 |
1873(明治6)年開校の小山小学校(現 小山第一小学校)のことだろう.市役所のすぐ南に位置する.校門前に道標がある.
"明治より学校建築にて進歩の駅なり"(上野下野道の記) |
小山第一小学校 |
 |
2024 |
| 慈法寺 |
じほうじ |
上野 |
小山市宮本町2-13 |
真義真言宗持宝寺が正しい.弓削道鏡の開基とされる.山門の上には鐘楼が見える.孝謙天皇の名が刻まれた鐘は,そこに吊されているのだろか.女帝孝謙天皇に取り入って,天下をうかがった道鏡.古川柳や小咄では,巨根の持ち主というのが共通認識になっている.下野に流された道鏡の墓は,国分寺町薬師寺の龍興寺にある.
"浄土宗 慈法寺 大寺なり"(上野下野道の記) |
持宝寺 |
 |
2024 |
| 喜沢村 |
きざわむら |
上野 |
小山市喜沢 |
壬生街道との追分に,天保6年建の男体山碑の道標,馬頭観世音碑と日清日露日支出征馬碑が並んで建つ.道標には"右奥州 左日光"とある.この道標に惑わされて,圓朝は"日光"とある左手の壬生道に入ってしまったらしい.旅人が壬生道に奪われることを恐れた奥州街道側の住民によって,倒されては再建が繰り返され,明治44年には日枝神社境内に移されていた.
"此の駅より 十七、八町 来たりて喜沢村に小休み"(上野下野道の記) |
喜沢追分男体山碑 |
 |
2024 |
| 黒本村 |
くろもとむら |
上野 |
小山市黒本 |
黒本は思川対岸に位置するので,直接の経路ではない.黒本集落の入口各所には,ワラジのような魔除けが竹に刺してある.
"是より左に付きて 十六、七町 来たれば黒本村三盃村にて小休み"(上野下野道の記) |
黒本方向を望む |
 |
2024 |
| 三盃村 |
さんぱいむら |
上野 |
小山市三拝川岸 |
三拝川岸.道を間違えた圓朝のルート.かけつけ三盃ではなく,富士筑波日光三山を拝めることからついた地名.以前の訪問では桑畑が広がっていたが,だいぶ少なくなってしまった.
"是より左に付きて 十六、七町 来たれば黒本村三盃村にて小休み"(上野下野道の記) |
三拝川岸神明宮 |
 |
2024 |
| 半田川 |
はんだがわ |
上野 |
小山市 |
姿川のことらしい.橋名は半田橋とある.半田橋を過ぎてさらに思川を渡ると,別項の黒本に入る.
"是従り半田川を越 舟渡 して並木を過ぎ"(上野下野道の記) |
半田橋 |
 |
2024 |
| 飯塚駅 |
いいづかえき |
上野 |
小山市飯塚 |
姿川を渡って,すぐに北へ道をとる.飯塚にある摩利支天塚と琵琶塚古墳は前方後円墳というが,小規模の盛り土だと素人には史跡としてのありがたさがわからなかった.飯塚の一里塚は,両側に土盛りが残っている.ただし,圓朝は一里塚の手前で東に曲がって軌道修正したらしい.
"並木を過ぎ、飯塚駅に休む"(上野下野道の記) |
飯塚一里塚 |
 |
2024 |
| 紫村 |
むらさきむら |
上野 |
下野市川中子 |
下都賀郡国分寺町が合併して下野市となっている.天平の丘公園に3基の五輪塔が並んでおり,紫式部の墓と伝える.明治初期に移設されたもの.紫の地名の方が先にあり,紫式部に由来したものではない.
"此処を出て紫村川名子より小金井駅に出るに"(上野下野道の記) |
伝紫式部墓 |
 |
2022 |
| 川名子 |
かわなご |
上野 |
下野市川中子 |
川中子(かわなご)が正しい.圓朝がどこで半田川を渡って川中子に入ったかははっきり読み取れない.次項の古泉観音堂に出るならば,御使者橋よりは南になろう.紫色に塗られた紫橋から川中子集落が見えるが,圓朝が書いているような山道というほどではない.
"此処を出て紫村川名子より小金井駅に出るに"(上野下野道の記) |
紫橋より川中子 |
 |
2024 |
| 生馬頭観音堂 |
いきばとうかんのんどう |
上野 |
下野市川中子 |
岩波版のルビは,しやうばとうくわんおんだう.小泉観音についても,"せうせんくわんおん"とあるので,ルビはあてにならない.川中子の集落に実在する古泉(こいずみ)馬頭観音堂.道に迷った圓朝の通った経路を知る鍵になる地点.
" 左に曲り 生馬頭観音堂に参拝して右の方山路を左にとりて"(上野下野道の記) |
古泉馬頭観世音 |
 |
2024 |
| 小金井駅 |
こがねいえき |
上野 |
下野市小金井 |
小金井一里塚は国史跡.拡幅された国道4号(日光街道)が一里塚を避けたため,両側の塚が残っている.生えているのは,エノキとイチイの木.東北本線小金井駅から徒歩圏.
"雑木山を 二十町ほど ぬけてやうやう小金井駅に出でたり"(上野下野道の記) |
小金井一里塚 |
 |
2024 |
| 大林寺 |
だいりんじ |
上野 |
小山市飯塚1582 |
台林寺が正しい.天台宗報恩山理性院.大林寺と次項の妙典寺の2ヶ寺は,飯塚にあり,妙典寺の方が手前になる.このあたりで,迷った道を修正している.
"天台 大林寺 法華 妙伝寺二ヶ寺ありと聞きしより尋ね往かんとする"(上野下野道の記) |
台林寺 |
 |
2022 |
| 妙伝寺 |
みょうでんじ |
上野 |
小山市飯塚1691 |
日蓮宗妙典寺が正しい.奉納された大釜で雨水を受けているのがユニーク.こんなふうに水がたまっていれば,「釜どろ」にも盗まれまい.
"天台 大林寺 法華 妙伝寺二ヶ寺ありと聞きしより尋ね往かんとする"(上野下野道の記) |
妙典寺 |
 |
2022 |
| 虚空蔵菩薩 |
こくうぞうぼさつ |
上野 |
下野市か |
未詳.このあたりにいくつかある星宮神社は,神仏習合として虚空蔵菩薩を祀っていた.
"神社は虚空蔵菩薩 祭礼ハ九月十三日 なり"(上野下野道の記) |
|
|
|
| 慈元寺 |
じげんじ |
上野 |
下野市小金井1-26 |
金剛乗院多宝山慈眼寺が正しい.真言宗智山派.小金井の寺院の覚え書きに,2ヶ寺があげられている.将軍日光社参の際の昼食場所としての寺格をもつ.
"寺院は慈元寺 真言"(上野下野道の記) |
慈眼寺 |
 |
2024 |
| 蓮行寺 |
れんぎょうじ |
上野 |
下野市小金井 |
日蓮正宗珠栄山蓮行寺.街道の東側にあたる.
"蓮行寺法華 あり"(上野下野道の記) |
蓮行寺 |
 |
2024 |
| 笹原新田 |
ささはらしんでん |
上野 |
下野市笹原 |
笹原だった土地を開発して新田とした.現在の地名は,もとの笹原となっている.国分寺町などが合併後,下野市役所が新設されたことで,旧日光街道がそこで分断された.市役所敷地内の日光街道の案内板に,ここが笹原新田であったことと,発掘調査で側溝をもつ街道跡が見つかったことが記されている.圓朝はここから筑波山を遠望した.明治の初めにはよく見えた筑波山も,ビルにさえぎられてしまい,新幹線の車窓からしか望めない.
"是より笹原新田に来たりて小休みの折から、夕立かかりて雷鳴なり"(上野下野道の記) |
下野市役所 |
 |
2024 |
| 下石橋村 |
しもいしばしむら |
上野 |
下野市下石橋 |
旧石橋町は合併して下野市になった.下石橋には,地名の由来となった石橋や一里塚があった.東塚は失われたが,忘れられていた西塚が"発見"された.あかみちと呼ばれる地番にない土地を進むと,林の中の石橋一里塚に至る.保存会によって大切に守られていることがわかる.
"下石橋村にいたれば千里軒の馬車の立場あり"(上野下野道の記) |
下石橋一里塚 |
 |
2024 |
| 石橋の駅 |
いしばしのえき |
上野 |
下野市石橋 |
旧石橋町.日光街道の宿場.石橋山開雲寺は,将軍日光社参の御殿跡.葵の御紋が掲げられた山門の袖塀に,四角い銃眼がくりぬかれている.
"少し休みて石橋の駅まで八町急ぎ本陣伊澤方に着きぬ"(上野下野道の記) |
開雲寺山門 |
 |
2024 |
| 本陣伊沢方 |
ほんじんいざわかた |
上野 |
下野市石橋 |
斜め向いの本陣も伊沢家だが移転した.隅に小祠がある.脇本陣だった伊沢写真館も看板が外されてしまっていた.
"少し休みて石橋の駅まで八町急ぎ本陣伊澤方に着きぬ"(上野下野道の記) |
脇本陣 伊沢写真館 |
 |
2024 |
| 上町 |
かみまち |
上野 |
下野市下古山 |
岩波版のルビは,うへまち.石橋は,上中下町に分かれていた.上町(かみちょう)が正しい読み.
"貸座敷上町下町とに有り繁盛の駅なり"(上野下野道の記) |
上町バス停 |
 |
2024 |
| 下町 |
しもまち |
上野 |
下野市石橋 |
岩波版のルビは,したまち.今は上町,本町,栄町,石町からなる.
"貸座敷上町下町とに有り繁盛の駅なり"(上野下野道の記) |
|
|
|
| −経路外− |
| 結城 |
ゆうき |
上野 (他 東京2件) 全2件2題 |
茨城県結城市 |
結城紬の産地.落語では,結城ぞっきなどの用例もある.紬問屋の奥順は,見世蔵などが国登録有形文化財になっており,結城紬の製法などを公開展示している.見学有料.「明烏」の坊ちゃんが吉原のお籠もりに着ていった結城紬は,かつては普段着とされていたが,今では一反100万円以上もする伝統工芸品.ユネスコの無形文化財に登録された.
"元木戸より右結城道"(上野下野道の記) |
結城紬 |
 |
2011 |
| 天明 |
てんみょう |
草三, 上野, 後日譚(岩波) 全2件2題 |
佐野市 |
天明鋳物は,佐野の特産として名をはせた.鋳物工場の数は激減している.正田家別邸があった地(JA佐野)には,鋳物工場の様子を示す銅板プレートが掲げられている.現存するが,年月を経てしまい,写真のような鮮やかさは失われた.
"宿(しゅく)の中程に佐野天明の別みちあり"(上野下野道の記) |
正田家鋳物工場跡 |
 |
1997 |
| 壬生駅 |
みぶえき |
黄薔薇, 上野 全1件1題 |
下都賀郡壬生町 |
圓朝は間違って壬生道に入ったが,壬生まで行かないうちに道を修正した.壬生藩の城下町.飯塚一里塚に続き,壬生一里塚(国史跡)もよく保存されている.西側の塚が残っており,塚上にはエノキが植えられている.壬生城主は日光社参の将軍を此処で出迎えたという.
"道を問へば、此所は日光道中にて壬生駅に出る本道なりと云ふ"(上野下野道の記) |
壬生一里塚 |
 |
2024 |
| 二里木 |
にりき |
上野 |
鹿沼市楡木町 |
楡木(にれぎ)と書く.例幣使街道と壬生通り日光街道の追分.Y字の股のところ,ガードレールに目隠しされるように道標が立っている.
"亦 二里木那須原加沼へ行く道と云ふ"(上野下野道の記) |
楡木追分の道標 |
 |
2008 |
| 那須原 |
なすはら |
上野 |
鹿沼市奈佐原町 |
奈佐原(なさはら)が正しい.例幣使街道の宿場.楡木から約2キロほど北になる.郷土芸能としての文楽が盛んで,太功記十段目,傾城阿波の鳴門巡礼歌,壺坂を得意とする.栃木県に残る唯一の三人遣い人形浄瑠璃で,県の有形文化財に指定されている.
"亦 二里木那須原加沼へ行く道と云ふ"(上野下野道の記) |
奈佐原文楽用具収蔵庫 |
 |
2025 |
| 筑波山 |
つくばさん |
蝦夷錦, 草三, 八景 など (他 東京64件) 全78件41題 |
茨城県つくば市,真壁郡真壁町,八郷町 |
江戸の丑寅彼方にそびえる双耳峰.見る角度によって,ちがった山容を見せる.「蟇の油」の口上,筑波颪,「陽成院」の筑波嶺など,落語でも頻出する.
"右の方に筑波山を見る景色尤もよし"(上野下野道の記) |
筑波山 |
 |
2021 |
 4日目
4日目 
 上野下野道の記 本文
上野下野道の記 本文